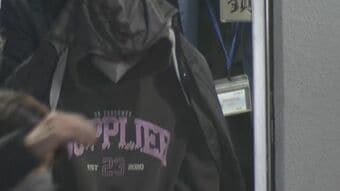「引っ越しを寂しがっているのかな」死者の存在を身近に感じる怪談話
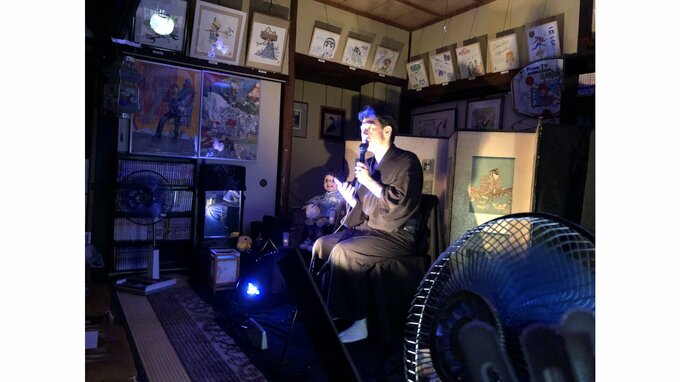
宇津呂さんには特に印象に残っている怖い・不思議な体験がある。
宇津呂鹿太郎さん
「阪神淡路大震災で大きな被害が出た界隈に10年間、住んでいた方のお話です。その方が家を引っ越すことになり、その前夜シャワーを浴びていると『バンッ・・・バンッ・・・』と板を叩くような音がしたというんです。
聞いたことがない音に驚いて、ゆっくり湯舟の方に目をやると、細長い子どものような手が見えたというんです。今までも何かがいるなという気配を感じてはいたそうなのですが、家を出る前の日にだけそんな事が起きたので、引っ越ししてしまうのを寂しがっているのかなと思ったそうです」

未曽有の災禍をもたらす戦争や自然災害などのあとには、死者の存在を身近に感じる話が多く生まれるという。この怪談を売りに来たのは、自身も阪神淡路大震災で被災した人だった。
東日本大震災でも被災地では怪談話が相次いだそうだ。多くは呪いや祟りなどの類ではなく、扉がガタガタ動くなどのちょっとした違和感や、身内が夢枕に出てくるなどだったという。
なぜ厄災と怪談が結びつくのか。宇津呂さんは語り手の奥底にある思いが反映されているのではないかと話す。
宇津呂鹿太郎さん
「戦争や震災では不本意な亡くなり方をした方が多くいます。残された人たちは、突然の死を受け入れられなかったり、悔しさや憤りを抱えていることが多くあります。怪談には、そんな残された人たちが、亡くなった人たちを気にかけ、思いを馳せる、鎮魂の意味合いもあるように感じます」
さらに、怪談を聞くということは「背景となった戦争や災害などを後世に伝えること」に繋がるのではないかと宇津呂さんは感じている。

宇津呂鹿太郎さん
「悲惨な出来事は経験した人々の記憶には深く刻まれますが、経験していない人には、なかなかつながりません。しかし、怪談というみんなが興味のある物語になることで、きっかけは別でも、その背景にある厄災についても知ってもらう機会になりうるのではないかとも感じています」
本当に幽霊がいるのか…。それはもちろんわからない。しかし科学的に説明できないからといって、まんざら架空の物語ともいえないのかもしれない。不本意な亡くなり方をした人たちが多くいて、その人たちを思い続けながら生きている人たちがいる。亡くなった人への思いが込められた怪談は、時空を超えて、かつてと、今をつなげようとする試みなのかもしれない。そう、まるで、幽霊のように…。