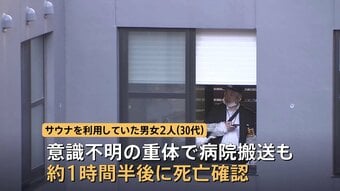■「普通の生き方が分からない」 社会復帰の課題
この女性は、薬物や詐欺などの犯罪で服役を繰り返してきた70代の元受刑者。
元受刑者の女性
「私は薬をやることが生きがいだったから。(警察に)捕まろうが何しようが捕まらないようにやる。(刑務所で)矯正教育してもらっても矯正にならないんだから」
15年近い刑務所での生活で、ミシンでの刑務作業や更生プログラムを受けてきましたが、「社会に出て活かすことができなかった」と話します。
元受刑者の女性
「ずっと悪いことして食べてきて何ができると思います?刑務所でパソコンをやらせてもらったんが、横文字・アルファベットが駄目、学校行ってないから。普通の生き方がわからない」

専門家は刑務所の改善とともに「社会の中での出所者の支援が重要だ」と指摘します。
慶応大学法学部 太田達也教授
「刑務所における矯正処遇の充実と社会における処遇の充実。この2つを有機的に連携させることが受刑者の改善・更生や再犯防止にとって非常に重要だ」
制度だけではなく、実効性のある受刑者の支援が求められています。
■「懲罰から更生へ」115年ぶりの法改正
小川彩佳キャスター:
刑務所での高齢化も深刻になっていて、明治以来の刑罰の在り方・法律と実態が合わなくなってきているという側面が大きいようですが、今回の法改正の他にどんな背景があるのでしょうか?

国山ハセンキャスター:
刑法犯のうちに占める再犯者率のグラフです。
年々増加傾向にありまして、2020年は過去最悪の49.1%でした。今回の改正案では犯罪の抑止を重視しまして、「懲罰から更生へ」と軸足を再犯防止に移行させるという意図があります。
刑務所内のリハビリなどが紹介されていましたけど、慶応大学の太田教授は「犯罪が多様になるなか、刑務所の処遇も多様化していく必要がある」と話していまして、刑務所での指導の質をどう向上させていくかが鍵になっていくと話しています。