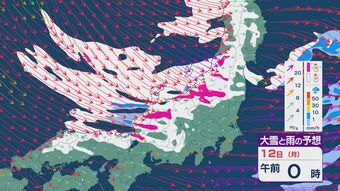それぞれの学校は夏休みに入っていますが、今回注目するのは、小学校で育てられているウサギやニワトリなどの「飼育動物」についてです。かつては当たり前に見られた光景ですが、それが今、教育現場の変化とともに少しずつ変わってきています。
つぶらな瞳に、丸みを帯びたフォルムが何とも愛らしい「ウサギ」。金沢市の夕日寺小学校の玄関先で飼育されている、オスの「ななみん」と「あゆみん」です。

児童「おはようございます!」
夏休みの真っ只中、午前8時半。登校してきたのは4人の児童たちです。子どもたちに生き物への親しみを持ち命の大切さを学んでもらおうと、夕日寺小では毎朝、4年生42人が当番制で世話を行っています。

世話をする4年生の児童は…
「あゆみんとななみんの毛がとてもモフモフしているところが好きです。すのこの汚れを落とすのが大変…」

簀子に付いたフンを水で洗い流したり、えさを取り替えたりとどれも地道な仕事ですが、子どもたちはやりがいを感じながら黙々と作業をこなします。

児童たちは、1年生から6年生はみんな学校に来る時にここを通るので、ウサギがもしいなくなったら寂しい」と話します。
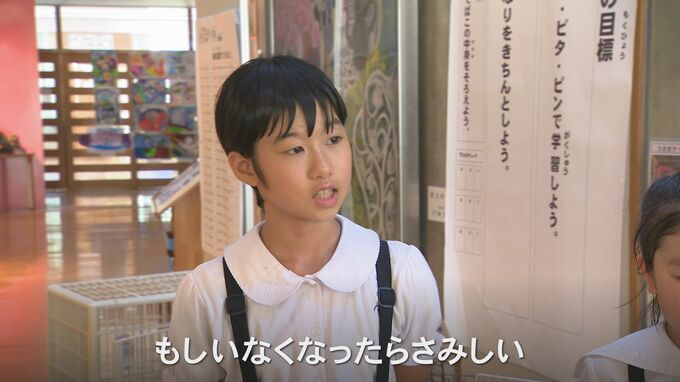
夕日寺小・山口久代校長
「児童は4年生になったら、自分たちがお世話をするというのをずっと見てきているので、今度は私たちが頑張る番という思いで世話してくれている。夕日寺小にとっては、命の大切さや自分が責任を持ってこの子達を世話するんだという気持ちを養うことができる」

一方、夕日寺小のようにウサギを育てる学校は、減少の一途を辿っています。金沢市内の小学校で飼育されていたウサギは、この10年で3分の1に減少。飼育する学校の数も半減しました。その背景にあるのは、「教員の働き方改革」。休日の餌やりなど教員の負担を軽減するため、やむを得ず飼育を断念したことなどが要因の一つに挙げられるといいます。

明治時代に始まったとされる、小学校での生き物飼育。小学校の生活科の学習指導要領には、「動物を育てる活動を通して生き物への親しみを持ち、大切にしようとする」との記載があります。その一方で…。

金沢市教育委員会・学校指導課 大井山武指導主事
「子どもたちには生き物を育てる活動を通じて、自分たちと同じように生きものには命があること、そして成長する喜びを感じて生きものを大切にしようという気持ちが育ってほしい。ただ、飼育に関してはそれぞれの学校の実情に合わせて対応していただいている」