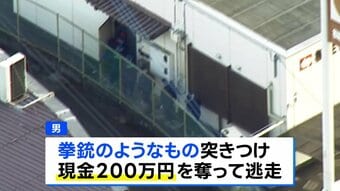日本銀行が植田新総裁のもと、『異次元緩和』から『普通の緩和』に向けて、そろり一歩を踏み出しました。小さな一歩に過ぎませんが、正常化に向けた貴重な一歩です。
YCCを修正し、運用を柔軟化
日銀は29日、政策決定会合で、10年の長期金利の上限を、今の0.5%から変えないものの、金利操作を柔軟化し、市場動向に応じて、これを超えることも容認することを決めました。また、1.0%で無制限に国債を買い入れることも決め、1.0%以上の上昇は容認しない姿勢を明確にしました。
事実上、長期金利の上限を0.5%から1.0%に変えたと受け取れる決定なのですが、これを「上限引き上げ」「利上げ」と呼ばれたくないのでしょう。日銀は、あくまで「緩和継続のための運用の柔軟化」と説明しています。
長期金利目標は投機のターゲットにされる宿命
長期金利コントロールの最大の問題は、ひとたび市場が金利上昇を見込んで国債を売り始めると、日銀が無制限に国債を買い入れなければならないことです。それでも売り圧力が収まらなければ、上限金利の引き上げに追い込まれてしまいます。現在のように、世界的にインフレ率が上がり、長期金利に上昇圧力がかかる中では、日銀は常にそのリスクに晒されています。
最終的な『壁』を、0.5%から1.0%にしたことで、そうしたリスクに対してかなりの「のりしろ」が生まれます。また、最終的な『壁』が1.0%であっても、目標はあくまで0.5%ですし、0.5%から1.0%の間にも、いつ『壁』があるかわからないという状況を作り出すこともできます。1.0%を待たずに日銀が介入してくる可能性はいつでもあるからです。
新たな『壁』を明示的に作って、投機筋に目標を与えるよりも、『壁』をあいまいにすることで、逆に長期金利の上昇を緩やかなものに留めることを狙った戦術です。