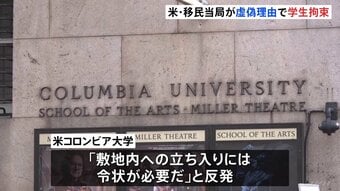「親が子どもを食ったって話だ」 住民が語る沖縄戦の実相
その実相を表したという彫刻が金城さんの作品にある。

タイトルは「摩文仁ヶ丘」。父親が、抱える子どもを食べているかのように顎を胸に食い込ませている。なぜ「摩文仁ヶ丘」なのか。
金城実さん
「親が子どもを食ったって話だ。国が民を食ってる。民は民の子どもを食った。そこに気がついてますか」
沖縄戦は、多くの住民が避難している南部に日本軍が撤退したことで、多大な住民犠牲を引き起こした重い事実を持つ。軍隊は住民を守らないという教訓を生んだ。
摩文仁を望む真栄平に暮らしていた当時14歳の大城藤六さん。集落の人々と避難していたガマに日本兵がやって来たのは、摩文仁の丘に日本軍が司令部を移す直前のことだった。
大城藤六さん
「すぐみんな出ろと、この2、3日に。最初はいい言葉を使ってこの戦に勝つために皆さん協力してくださいと。皆さんを守るために中部から兵隊が来ますから出てください。出て行ってからが犠牲者が多かったですね」
住民は戦場に投げ出された。そして、戦後、集落に広がった光景は、遺体と遺骨の山だった。
大城藤六さん「畑に行っても出てくる。道を掃除しても出てくる。溝を掃除しても出てくる。どんどん増えるんです」
収容した深さ3メートルの穴から遺骨はあふれていた。そこに蓋をした納骨所は、その後、南北の塔となった。

沖縄にとっての慰霊の対象は、住民の手による骨塚だった。この骨塚を整備した納骨堂こそ、住民の祈りの場だ。
しかし、遺骨の運命は急変する。日本政府や琉球政府の方針で、一か所に集約されることになったのである。
真栄平の住民はこれに強く反対した。
大城藤六さん
「焼いて小さくしてから持って行くという。戦で焼かれてまた焼かれるのかと。これは自分たちの身内の者が入っていると。村の村墓だと」
だが、拒絶する住民の意思は顧みられることなく、大城さんによると、いつの間にか遺骨は運び出されていた。

最終的に、摩文仁の丘の中央に位置する国立沖縄戦没者墓苑に収容された。
住民の遺骨は、兵士の戦死を称える殉国の丘に同居することになったのだ。
その流れの背景には、ある法律の存在があった。
援護法適用で「亡くなった住民」は「戦闘参加者」に
戦傷病者戦没者遺族等援護法。戦死者の遺族などへの年金支給の法律が、占領下の沖縄にも適用されると、その後、対象は軍人・軍属だけでなく民間人の犠牲者に広がった。
援護法の住民への適用は、沖縄の遺族連合会も強く望んでいた。そして、国は「亡くなった住民」を「戦闘参加者」として遺族が援護金を申請する仕組みを作った。
例えば「壕を追い出された」のは、「壕を提供した」ことに、強制集団死やスパイ容疑での虐殺も軍の機密を守るためだったことにして、0歳児まで軍に協力した戦闘参加者として申請させ、遺族に援護金が支払われていった。
死の理由が書き換えられてできた戦闘参加者の名簿は、厚生省から靖国神社に提供され、一般住民が軍人軍属と同じように合祀された。こうして住民の犠牲は国に殉じた死に囲い込まれる形となったのだ。
石原名誉教授は、沖縄戦の事実の歪曲を危惧する。

沖縄国際大学名誉教授 石原昌家さん
「見事にからめとっていってるわけですね。援護法で軍民一体の適用を受けたらもう一般住民はいないんですよ。すべて戦闘参加者でね。そういう流れの中で具体的な形として沖縄戦没者墓苑が出来上がってしまったと。まさにこれは靖国化、靖国を象徴するような形になってしまってるわけですね」