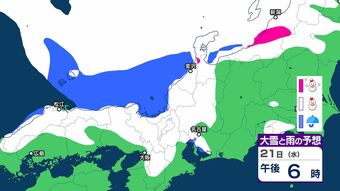魚屋は甘くない!?
記者が取材した日は、マイワシ、カサゴ、メジナ、カツオ、イサキのほか、キビナゴ、ヤガラ、月日貝といった、この辺では珍しい魚や貝も並びました。鹿児島出身の記者にとっては、なつかしい魚ばかりです。最寄りの大型スーパーは、車を運転していくか、バスで20分。最近、買い物に困っていたというお客さんが、次々に訪れます。
「25年ぐらい住んでます。最初来た時はね、よかったんですけど、もう次から次と閉店になっちゃって、ちょっと『陸の孤島』みたいになっちゃってるから、起爆剤になるといいなあ」
「みんなで寄付したんです。すごく鮮度がいいし、一生懸命やってるから、自分たちのためにも、応援がてら」
「山だし、お魚屋さんないので、とっても嬉しいです。いっとき子供たちがいなくなって、人口も減って、寂れかけたんですよね。でも、町内会の会長さんやなにかがね、頑張ってくださって、子供たちも戻ってきて。徐々に盛り返してきてるようで、嬉しいですね」
お客さんと楽しそうにやり取りする、店長の田島さんですが、「準備も片づけも大変で、魚屋は甘くはないな」というのが率直な感想です。「サカナヤマルカマ」のスタッフは、今泉台の住民とそうでない人が半々。20代から60代。魚好き、釣り好きだけど、魚屋経営は素人の住民。料理人だが魚屋は素人。多彩なメンバーで、魚の見極め、処理の仕方、裁き方、売り方、魚の種類、刺身や総菜の調理など、これまでも勉強してきました。

移動販売も行い、地域の課題解決の拠点にも
移動販売の時から、阿久根と鎌倉の橋渡し役となっているのは、鎌倉市内の別の地域に暮らす、狩野真美さん。広報・営業を担当する狩野さんは「発起人たちも魚の素人であるがゆえ、逆に、消費者にすごい近い部分があるので、そこの意識をちゃんと大切に持ちつつ、でもちゃんとプロがいて。教えてくれる人がいる。あと、料理人が今回多いので、魚について勉強したいっていう気持ちが強い。うまくほんとみんなでバランスを取りながら、みんなで成長していこうという、魚屋ですね」と話します。まだまだ勉強は続いています。
また、街に暮らす高齢者の中には、商店街まで足を運びにくい状況の人もいます。「サカナヤマルカマ」は、この店舗を拠点にして、6月から、今泉台や鎌倉市内の同じような状況の住宅地で、「移動販売」を始める予定です。また、お客さんの中には、最近、また子供の声が聞こえるようになったと話す人も多く、子育て世代向けのおさかな教室やイベントも考えています。
「街のお魚屋さん」が、地域の課題解決や、地域同士の連携を進める、という事例になるかもしれません。

TBSラジオ「人権TODAY」担当 崎山敏也(TBSラジオ記者)