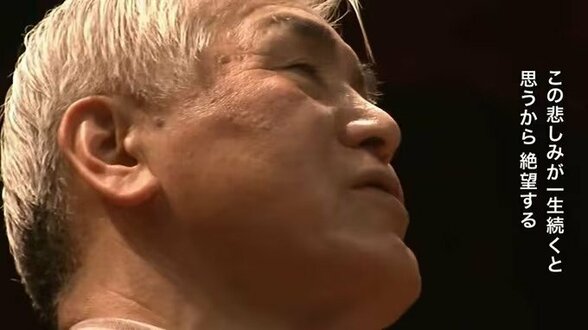日本株が評価された理由とは
日本株がなぜ選ばれたのか。まずベースとして、日銀の緩和姿勢が変わらないという安心感が広がったことでしょう。
植田総裁に変わって、すわ政策転換かと身構えたものの、当面は「変化なし」と、市場は判断しました。為替市場も円安で推移していて、総じて日本企業の業績にもプラスです。
そして、その企業業績が、2023年3月期の決算を見ても全体としては非常に好調です。コロナからの経済活動再開で非製造業を中心に期待以上の好業績で、24年3月期も全産業で見れば増収増益が見込まれています。
その背景にあるのが、「物価も賃金も上がり始めた日本」という海外投資家の認識でしょう。物価も賃金も凍り付いていた状態が正常化に向けて動き始めたという期待です。物価が上がることが経済成長や業績向上につながると見ているのでしょう。
そうした期待を端的に表しているのが、アメリカの著名投資家ウォーレン・バフェット氏の「日本株推奨」です。日本の総合商社株に投資したバフェット氏が日本を訪れ、追加投資を表明したことは、世界中の投資家の多くの注目を集めました。
さらにここに来て、東京証券取引所がPBR1倍以下の上場企業に対し改善措置を求めていることも影響しています。
PBRとは「株価純資産倍率」のことで、これが1倍以下だと事業を続けるよりも、資産をすべて売り払って会社を解散した方が株主にとって得、という数字です。
東証のこうした要請を受けて、東京市場では自社株買いがブームになっており、それが株価を押し上げている面もあります。
もちろん、「内部留保」を「自社株買い」にあてるだけでは企業は成長しませんが、少なくとも株主を意識した経営に変わりつつあることが、投資家には評価されているのです。
日本の変化の芽に注目も、米景気には警戒が必要
こうして見てくると、いわゆる「稼ぐ力」を含めた日本企業や日本経済の変化が、それなりに評価を受け始めたという面があるのです。
その一方で、株価の先行きに警戒は必要です。アメリカの景気後退が現実のものになれば、日本の株価にも影響は避けられません。
グローバル経済の後退局面では、生産財輸出を得意とする日本経済は、想定以上に大きなダメージを受けます。依然として先行きに慎重な見方をする市場関係者は多くいます。
前回の2021年の時には、3万円台の「滞空時間」は、短いものでした。その3万円台が定着するかどうかは、海外投資家たちが目ざとく見つけた日本経済の変化の良い兆候を、どれだけ定着させて行けるかにかかっています。それは、「バブルとその清算の時代」を越えていくための、必要な過程です。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)