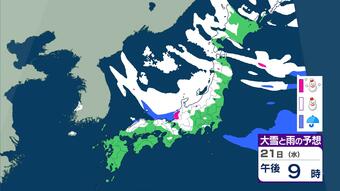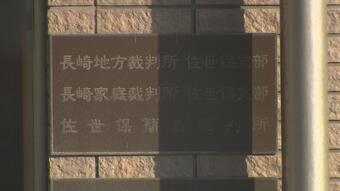日本の水産を変えるモデルケースに
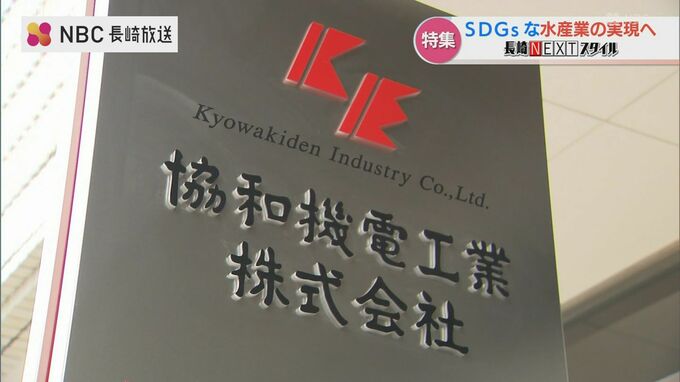
こうした課題の解決に向けて、ながさきBLUEエコノミーには県内外の企業や地元自治体も参画しています。長崎市の協和機電工業も、そのうちの一社です。

協和機電工業 坂井 崇俊 代表取締役社長:
「この長崎を何とか盛り上げていける事業がないかということで、その一つが水産業、というところに目を付けて、長崎大学さんと一緒に、自治体も含めて取り組んでいきたいというところから、スタートしております」

洋上発電をはじめとした、海洋関連機器の開発などを手がける協和機電工業では、沖合養殖で使用する電源の確保などに、自社の技術を役立てたい考えです。

坂井 社長:
「県外、全国、海外でいま仕事をしているんですけど、色んな方が長崎に来て、やはり魚を食べた時に『美味しい』と言っていただけますので、それは一番大きな強みだと思いますし、それが今後BLUEエコノミーを通して、”健康”というキーワードが入ってくれば、なおより高付加価値なものになっていくんじゃないかな、と思ってます」
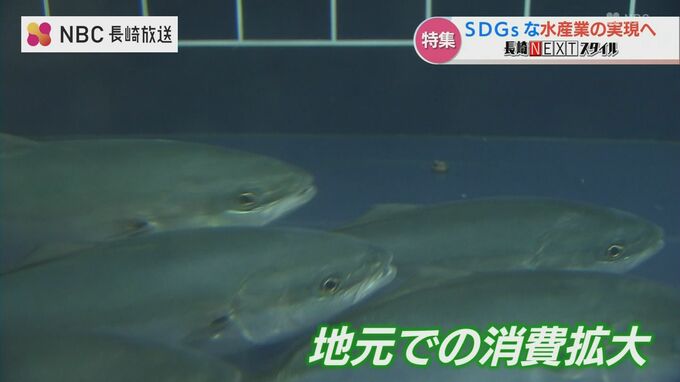
ながさきBLUEエコノミーでは、地元での消費拡大も視野に入れています。
長崎は地産地消の核となる販売拠点がまちなかに少ないことから、生産者が農水産物を持ち寄る施設を新たにつくり、県民や観光客が手に取りやすい環境を整える計画です。

大学と企業、そして自治体が連携し、水産業の再生という同じ課題に向き合う、それがながさきBLUEエコノミーの役割です。

長崎市水産センター 村瀬 二美 所長:
「今の長崎の水産業に非常に欠けている部分とか、課題となっている部分に切り込むような形になってるんですよね。これが上手くいけば、長崎の水産業に大きなインパクトを与えて、将来にわたって持続可能な産業になっていくと考えています」

このほど国の事業にも採択され、実現に向け大きく動き出した”ながさきBLUEエコノミー”。長崎、そして日本の水産を変えるモデルケースとなることが期待されています。