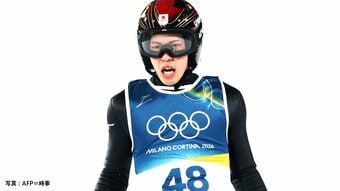水素ビジネスの取り組み。収益化はまず「商用」から。
ーー水素ビジネスへの種蒔き、どうビジネスして収穫するのでしょうか。収益を上げるという意味ではどう考えていますか?
水素エンジンも一つの選択肢ではあるんですけど、水素っていうエネルギーをどう使っていくかということだと思うんですね。その観点では、FCEV(燃料電池車)も水素エンジンも等しく水素をエネルギーとして動くモビリティになると。そのパワートレインによって、得意領域が違うので、使い方はそれぞれ運転特性に合わせて選択される。そういうことを考えたときに、現状の見通しからすると、やっぱり商用利用を優先させながら、水素を作る、運ぶ、使うのいわゆる全工程で、ビジネスサイクルというかいわゆるプラットフォームを作っていって、そこを収益に繋げていくということがおそらくビジネスモデルとしては、一番想定しやすいことなんだろうと思うので、水素利用のところはまず商用のところから切り口を作っていって、乗用利用に転用できるように技術改善を進めていくっていうそういうベースになろうかなと思います。
佐藤新社長に聞く、今後の注目ポイントは?
ーー「佐藤さんが社長になられてトヨタがこうなった」というのは、頭の中に置いて仕事に臨まれていると思いますが、今後どこが注目ですか?
私自身のバックグラウンドやっぱりエンジニアですので、この時代にエンジニアがいわゆるキャプテン役をやるということが、最もそのトヨタの変化の中で特徴的なことだと思うんですね。大きな土台を、現会長の豊田章男会長がしっかりつくってきてくれた。その土台の上に次の未来の進化を促していくときには、いろいろな新しい技術とか新しい発想で、いろんな挑戦をして、トライアンドエラーで物で示していく。
物がいろんなアイディアをまた産んで改善が進んでいくという、そういういわゆるリアルなもの作りの中で、作り込まれていく我々らしい価値というものが、これからのトヨタを示していくものになるんだろうと思うんですね。
だからこそ今、このタイミングでエンジニアである私がチームリーダー役を仰せつかっているということだと思うので、やっぱりクルマ、あるいは物で我々のあり方を見続けて頂けるとありがたいなと思います。
取材を終えて
「とにかくクルマが好きな社長」。社長就任が決まって以来、取材を続けて感じる印象はこの一言につきます。私生活では旧車のレストアを行っているとのことで、「社長就任以降は直接愛車をいじる時間がないのが悩み」と漏らしていました。そうした「クルマ」へのこだわりは、経営姿勢にも現れていて、会見のたびに自社のことは「クルマ屋」と発言し、変革の時代であっても自動車の生産会社であるこだわりを随所で見せています。
ただ、自動車産業をめぐっては厳しい道のりが続きます。脱炭素への対応は自動車メーカー各社が避けては通れない道のりになっていて、エンジンを拡張したハイブリッドで世界を席巻したトヨタも厳しい戦いに巻き込まれている状況です。
「クルマ屋」として、つくったクルマやモノづくりで評価して欲しいという佐藤新社長。脱炭素に向けた取り組みをどうやって形で示していくのか。本格化したEV戦略で出す「こだわりのクルマ」はトヨタの今後の経営についても大きな評価の対象となりそうです。