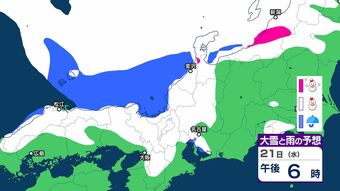改めて支援継続を決意
2020年のクラウドファンディングで集めた資金は今回で終わりでしたが、戻ってきて、2度目のクラウドファンディングを2023年の5月21日まで行うことを決めました。
群馬県太田市の一寸木大喜さん
「みんなに、このロヒンギャの問題のことを忘れてもらっちゃ困るっていう気持ちです。忘れちゃったら、もう次はないじゃないですか。でも、誰か少なくとも覚えていれば、どんどん次に繋げていくことができる。やっぱり、彼らのことと、彼らが抱えている問題のことを忘れないためにも支援を続けていくということはとても大切なことなんだと思います」
今回、4人と一緒に話を聞いたアウンティンさんも、大喜さんのこの説明に大きくうなずいていました。

忘れないことが大切
日本で暮らすアウンティンさんは、中古車や家電を輸出する会社を経営するほか、ロヒンギャのことを知ってもらう活動や、難民キャンプの支援を行い、イスラム教徒でも安心して食べられる「ハラール」のものを置いた食料品店とレストランも2022年にオープンさせ、国籍、宗教、文化を超えた交流に取り組んでいます。4人はアウンティンさんと同じ地域に暮らし、外国ルーツの子供は周りにもいないわけではないですが、ロヒンギャのことは具体的には知らなかったといいます。しかし、「僕たち私たちにできること」の活動を通じて、よくジュースやお菓子をくれる近所のおじさん、になっているようです。

多民族国家のミャンマーは、2年前に軍事クーデターが起きて、民主化勢力による抵抗が続いていますが、その前から不法移民扱いされ、ミャンマー国籍がなかったロヒンギャにとっては、どこに逃げても不安定な暮らしを強いられ、ミャンマーにいつ戻れるかも見通せない状況です。4人の活動について、アウンティンさんは将来への期待を込め、こう話します。
在日ロヒンギャ難民の1人、アウンティンさん
「子供達が忘れないということは、本当に素晴らしいことだと思います。忘れてしまったら、ロヒンギャたちを助ける人が誰もいなくなってしまいます。ロヒンギャ難民は国籍もないので、忘れられたら、どこに行けばいいのでしょうか。難民キャンプでもいろいろ生活の問題があります。世界の人たちが同じ人間として支援すれば、4人の子供たちのように学校関係で本とかノートとか、いろいろ支援を続けていれば、いつかは国に戻ることができると思います」
そして聡真さんも訴えます。
群馬県館林市の鈴木聡真さん
「いま支援をやめると、現地の子供たちは見捨てられた気持ちになるかもしれないし、教育がきちんと受けられないと、将来につながらない。支援を続けたいので、今回のクラウドファンディングに協力をお願いします」
と話していました。

(TBSラジオ「人権TODAY」担当:崎山敏也(TBSラジオ記者))