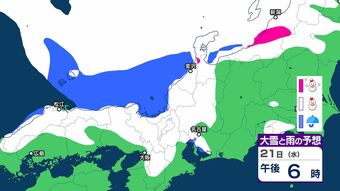ミャンマーの少数民族で、イスラム教徒がほとんどの「ロヒンギャ」。長年、ミャンマーの中では不法移民とされ、国籍が与えられていません。迫害により、難民になる人も多く、隣のバングラデシュにある難民キャンプには現在、100万人近いロヒンギャ難民が暮らしています。
今回は、こうしたロヒンギャ難民を支援する日本の小中学生を取材しました。
小学6年の時、始めた難民支援
食料や物資が充分とはいえないバングラデシュにある難民キャンプを2023年の2月、群馬県館林市の鈴木聡真さんと妹の杏さんらが訪れ、子供たちに、文具やサッカーボール、お手玉、お菓子などを直接渡してきました。この支援のための資金は2020年、当時小学6年生だった聡真さんらがクラウドファンディングで集めたものです。

聡真さんは新型コロナの流行で学校が休校になり、出された課題に取り組む中で、館林市に300人近いロヒンギャ難民が暮らしていることを知ります。その1人で、在日ロヒンギャ難民のリーダーの1人、アウンティンさんにロヒンギャ民族の歴史や現状、難民キャンプでの厳しい暮らしのことなどを聞いたことから、聡真さん、杏さんと同じ「ぐんま国際アカデミー」に通う一寸木大喜、悠喜さん(太田市在住)と一緒に、国際協力NGO「僕たち私たちにできること」として活動を始めました。大人に相談しながら、クラウドファンディングを立ち上げ、約300万円を集めました。
4人はアウンティンさんを通じて、難民キャンプの子供たちや学校関係者とオンラインで交流しながら、必要なものを聞き、これまで、パソコンや教科書、カバンなどを贈ってきました。そして、コロナ感染が落ち着いてきたこともあり、聡真さん、杏さんに母親の由希子さん、アウンティンさんらが同行して、バングラデシュにある難民キャンプを訪れたのです。
難民キャンプで感じたこと
その時のことを、聡真さん、杏さんに聞きました。
群馬県館林市の鈴木聡真さん
「インターネットとかに載ってる写真だとけっこうみんな暗い顔してて、あまり笑ってないイメージがあったんですけど、現地に行くと、僕たちを見るだけでなんか笑顔になってたりして、笑顔けっこう多いんだなって思いました。また、ちょっと前にあげた、まだ1年ぐらいしか経ってない教材を、本当に何十年使ったんだというぐらい、ボロボロになるまで使ってくれてたりしたのも印象に残りました」
妹の鈴木杏さん
「自分よりも幼い女の子がさらに小さい子の世話をしているのが印象に残った」

一方、現地の子供たちは、歓迎の言葉と共に「私たちはサポートが必要です」と書かれたボードを掲げ、具体的にどんなものが必要かも、話してくれたということです。