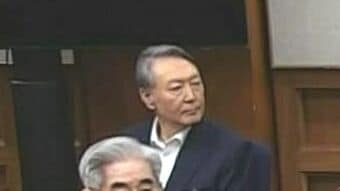“介護者同伴条件”が生まれたワケ
旧国鉄事情に詳しい交通政策が専門の関西大学・安部誠治名誉教授に、日本の鉄道における障害者割引制度の成り立ちについて話を聞いた。

関西大学 安部誠治名誉教授
「1980年代までは大都市圏では旅客の輸送力がひっ迫していて、東京だとひどい時には混雑率が300%ということもあったんです。複々線化をするなどまずは、輸送力を増強することが優先されたのです」

当時は障害者やバリアフリーへの理解が乏しく、財源も限られていたので、優先されたのは“健常者の移動手段の円滑化”だった。つまり、バリアフリーが整っていない駅での障害者の移動は介護者の存在が必須だったのだ。
関西大学 安部誠治名誉教授
「その後輸送能力が増強されて、1990年代後半からようやく障害者のためのバリアフリー化の方に目がいって、バリアフリー化が前に進む状況なってきた」
「障害者が一人で移動して社会参加できるというのが重要なので、駅のバリアフリー化はそのためにやっているわけですね」

では、バリアフリーが進み、障害者が一人で社会参加が可能になった現代では“介護者同伴条件”は時代遅れなのではないか。
“介護者同伴”は時代遅れ?
関西大学安部誠治名誉教授
「ヨーロッパなどの諸外国では障害者の単独利用割引を制度化しています。学割だと教育省、身体障害者割引だと日本の厚労省にあたる省の国家予算でまかなっている。今後、日本は障害者の一人外出が増えていくと考えられる。じゃあ、割引はどうする?ということを検討せざるを得ないことになるので、諸外国のように公的負担で障害者の単独利用での割引をやることが次の課題です。ようやく日本もそういう段階に来たのかなと思います」