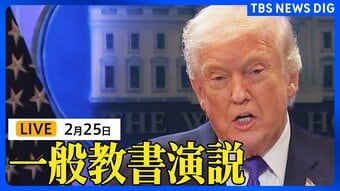この画像は東京都杉並区・下高井戸の駅前です。散乱するこれらはぜーんぶゴミ。ハエは飛び、悪臭は広がり、地面は「汚汁」でベトベト。東京のまちなかが文字通りゴミだらけになりました。ゴミ屋敷ならぬ、ゴミ街角……。信じられますか、1970年代の東京には、こんな一時期があったのです。
(アーカイブマネジメント部 疋田智)
ゴミはすべては「江東区におまかせ」
いまや世界的にトップクラスのゴミ処理の厳格さと、街にゴミが落ちていない清潔さが有名な東京ですが、これは決して、最初からこうだったわけではありません。かつての東京には、お互いにゴミを押し付け合い、ハエやネズミだらけの時期がありました。

「ゴミ戦争」の発端は江東区からの不満の爆発でした。戦後の高度成長を経由し、東京のゴミは増える一方。そのゴミのほぼすべては江東区の埋立処分場に埋められていました。
処理量の増大に、清掃工場の処理能力や工場自体の数が追いつかず、廃棄されるごみの約7割が未処理でそのまま埋め立てられるようになったといいます。

1950年代後半から1970年代前半に埋立中だった処分場が夢の島(14号埋立地)と新夢の島(15号埋立地)です。その夢の島の様子をマスメディアが報道したことにより「夢の島=ごみの島」という、負のイメージが植え付けられていきました。
不満爆発の江東区と「ゴミ戦争」の言葉
特に江東区の枝川地区では毎日運ばれるゴミの量が毎日トラック5000台にもおよび、運ばれたゴミがそのまま未処理で埋め立てられることになっていました。1971年、このような状況に江東区は「これ以上我慢できない」と不満が爆発し、美濃部亮吉都知事(当時)は、ゴミ処理について、なんとか対処すると宣言したのです。この際に出てきたのが「ゴミ戦争」という言葉。するとその言葉通り……。

杉並区が住民運動で猛反対
東京都が出した基本原則はこうです。「自区内で出たゴミは、原則、自区内で処理すること。各々の区は責任持ってゴミ処分場を区内に作ること」。ところが、新ゴミ処分場の予定地となった場所で、猛反対運動が起きました。中でも激しかったのが杉並区です。

杉並区の処分場予定地となった高井戸地区では「住宅の近くにゴミ処分場は困る」と、住民らが処分場建設反対運動を行い、その一部が都議会に乱入するなど、大騒ぎとなりました。
そして、1970年で本来終わるはずだった、夢の島および新夢の島(江東区)のゴミ埋立は、その後もなし崩し的に続くことになったのです。怒ったのはもちろん江東区。