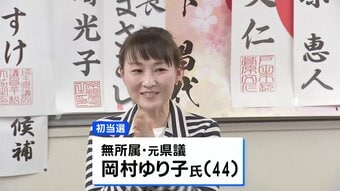驚くような発言はなかったものの、植田氏の問題意識が強くにじむ所信聴取でした。次期日銀総裁候補となった経済学者の植田和男氏に対する所信聴取が衆参両院で終わりました。日銀の審議委員の経験もある植田氏の答弁は安定感がり、答え方も丁寧でした。
緩和政策継続も、前向きな景気・物価認識
植田氏は、現在の日銀の政策と金融緩和の継続は適切であると改めて表明した上で、消費者物価上昇率が「23年度半ばには2%を下回る水準に低下する」と、現在の日銀の見通しを追認しました。緩和継続の理由付けをしたわけで、ここまでは想定内です。
その上で、現在の物価の動きに「好ましいものも出てきている」と指摘し、現在の物価上昇が賃金上昇を伴って、基調として2%の物価上昇が実現することに強い期待感を示しました。植田氏は「芽がある」という表現も使っており、植田氏の景気・物価に対する認識は、公式見解以上に「前向き」な印象を受けました。
副作用認め、「出口」にも言及
最も注目されたのは、その先の「出口」にまで言及したことです。植田氏は「2%の物価目標の実現が見通せる場合には、正常化に踏み出すことができる」と述べました。当たり前のことを言っているに過ぎませんが、これまで黒田総裁は出口論を口にすることさえ避けて来たので、植田氏の発言は、「論理的」で「わかりやすい」ものでした。
植田氏はまた、異次元緩和策に様々な副作用があることをはっきりと認め、「必要に応じて検討、検証を行いたい」と、踏み込みました。
副作用の最たるものである日銀による大量の国債購入についても、「2%の物価上昇が見通せるようになれば、大量の国債購入はやめることになる」と明言した他、日銀が主要企業の大株主になるなど弊害が指摘されている、巨額のETF=上場投資信託の保有についても「大きな問題である」と率直に認めました。黒田総裁の答弁ぶりとは大きく異なります。
長期金利目標の是正、「頭の体操」はすでに開始か
具体的な問題意識も垣間見えました。日銀は昨年12月に、10年の長期金利の変動幅を0.5%に拡大することを決め、世間を驚かせました。その今後について、植田氏は「現在は、その効果を見守っている段階」と慎重に言葉を選びながらも、「様々なオプションがあり、その一つ一つについて、今ここで触れることは差し控えたい」と、すでに具体的に頭の体操を始めていることをうかがわせました。まずは長期金利コントロールを是正し、条件が整えば、次にマイナス金利解除という頭の整理をしているのでしょう。
アベノミクス「踏襲」に配慮
そうは言っても、政治的には、「アベノミクス」や「リフレ派」への配慮は必要です。参議院での聴取では、安倍内閣で官房副長官や経済産業大臣を歴任した、安倍派の世耕弘成氏が、「アベノミクスを継承するのか」と植田氏を問い詰める場面がありました。
植田氏は、「デフレでない状況を作り出した」「緩和メリットが副作用を上回っている」とアベノミクスを評価しました。その上で、路線の継承については、「物価2%目標の達成を目指すという意味で踏襲する」と答えました。非常にうまい答え方だと思いました。
考えてみれば、金融緩和の内容だけでも、この10年間で様々なスキームが複雑に積み上がっている上、アベノミクスという言葉には、金融政策だけでなく、財政政策や成長戦略まで、様々なものが含まれていて、人や時期によって、定義も異なります。また、取り巻く環境も、時々で大きく異なっています。アベノミクスは「正しいか、誤りか」、「継承するのか、しないのか」といった議論で、いたずらに政治的対立を煽ることは不毛です。それよりも、デフレ脱却という大目標は変えずに、副作用の是正から手をつけていくというのが、植田氏の姿勢のようです。
政府・日銀の共同声明は「変える必要なし」
アベノミクスの原点である政府・日銀の共同声明についても、植田氏は、「現在、物価2%が達成されたとは言えないのだから、当面変える必要はない」と明言しました。これも、そうした基本姿勢からでしょう。
植田氏は「積年の課題であった物価安定の達成というミッションの総仕上げを行う5年間にしたい」と抱負を語りました。まさに、そうあって欲しいものです。日本経済をデフレの「出口」に導き、しかも「ソフトランディング」させるという難しい挑戦が始まります。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)