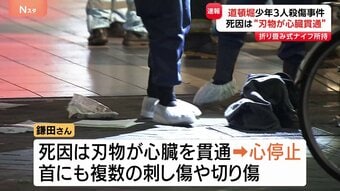■1970年代からインクルーシブ教育を実践 大阪・豊中市では

障害の有無などによって、学ぶ場を分けられることなく、子どもたちがともに学ぶことは「インクルーシブ教育」と呼ばれSDGsにも掲げられている。
アメリカで長年、障害者の社会運動に取り組み、インクルーシブ教育の重要性を訴えてきた
ジュディ・ヒューマンさんはこう語る。
元アメリカ国務省 障害者人権特別顧問 ジュディ・ヒューマンさん
「インクルーシブ教育は障害のある子だけではなく障害のない子にも有益です。障害のある子どもも適切な支援や配慮のもと通常学級に通うというのが原則であるべきです」
インクルーシブ教育が注目される前から実践してきた大阪府豊中市。 豊中市は1970年代から障害の有無にかかわらず、地域の子は地域の学校で受け入れてきた。
車いすに知的障害、自閉症や情緒障害など、さまざまな障害の子どもたちがいるが一緒に学んでいる。
野畑小学校 柴田裕子 前校長
「どのクラスにも2,3人はいる。わからないでしょ? 全然特別ではないから、それなりの支援は必要だけど」
クラスには支援を必要とする子をサポートする教員が入っている。ただ、支援担当の教員はいつも同じ子の近くにいるわけではない。
柴田 前校長
「助けが必要だなと思ったらそばに寄る、そうでなかったら離れる。教師が引っ付いていると他の子との壁になっちゃうじゃないですか、離れて見守っていると子どもたち同士がつながる」

医療的ケア担当看護師
「本人を見ていると周りの子の友達と接することで違う表情を見られる。周りの友達も優しい心を持って育っているのがわかります」
支援する教員が教科書を読み上げ、クラスの仲間たちが声をかけて一緒に学んでいる。
恵吾さんのクラス担任 徳常志穂教諭
「『先生いまこんな風に言っている』とか『これ困ってる』とか教えてくれる。長いこと小さな頃から知っているのは子どもたちにとってすごく財産なのかなとは感じます」