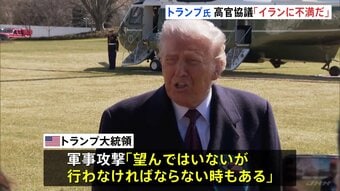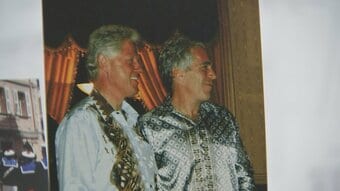クリミア併合に目をつぶっていたことが、今回の戦争を止められなかった…
1990年代、アメリカでは冷戦終了を受けて国防費を経済の回復に当てるべきという議論が沸き起こった。一般に『平和の配当』と呼ばれ、米ロ両国ともに軍事費は大幅に削減し、予算、人員、技術ともに民間に還元される流れがあった。しかし、この流れもすでに廃れ、今や各国軍事費は拡大路線を辿っている。
NATOの戦略分析の元責任者にインタビューした。彼女によれば『平和の配当』は2014年のロシアによるクリミア併合によって確実に終わっていたという。

元NATO戦略予見チーム長 ステファニー・バブスト氏
「ロシアによるクリミア併合後、NATOが加盟国に要求していたことは、国家レベルでNATOの演習及び作戦に利用できる十分な弾薬と戦力を確保し、最終的には備蓄を強化することだった。しかし一部の同盟国は軍備の増強を進めたが、多くの同盟国は実行しなかった。私の国ドイツがそのいい例だ。NATO加盟国は2014年以来、逆に弾薬を含む戦闘能力への財政投資を縮小してきた。そのためウクライナ侵攻後いまだに多くの国が備蓄の強化に苦戦を強いられている。(中略)クリミア併合後、備蓄を強化しなかったのは私たちの過ちだ。多くの指導者の過ちは『平和の配当』の終わりが来るのを見たくなかったということ。彼らはそれを認めたくなかった。彼らは経済的、ビジネス上、イデオロギー上…複数の理由で単に先延ばしした。ロシアに対し目をつぶっていたのだと思う」

ロシアがクリミアに侵攻した時、『平和の配分』は終わっていた。それなのにNATOの多くの国は軍備を縮小した。今、軍備を増強するなら、あの時にするべきだった。
元陸上自衛隊東部方面総監 磯部晃一氏
「バブストさんの話は我々にも突き刺さる。私は2015年に退官したが、日本の防衛費もそれまで20年間右肩下がりだった。弾薬などの購入費もどんどん落ちていた。ミサイル装備など正面装備といわれるものは増えたんですが、その分、後方支援、弾薬は減っていった。『平和の配当』の終わりを見たくなかったというのは日本にも当てはまる。現在も政府の試算によると(日本は)3か月防衛するために必要な弾薬の6割しか確保できていない」

日本の防衛費も今、大幅に増やす方向になっている。脱炭素のはずが石炭回帰になり、平和の配当を得るはずが軍備増強の方向に進むのに抵抗感が少なくなった。そしてもう一つ、最大の逆流、それは…