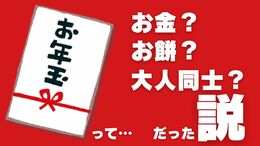10万を超える死者を出した関東大震災のわずか4年後の1927年、京都府北部・現在の京丹後市や宮津市などを中心に起きた奥丹後地震(北丹後地震とも)は、2,925人もの死者、1万2,584棟の全壊家屋を出す大惨事となりました。しかし当時のフィルムを見ると関東大震災と何かがまるで違っています。
(アーカイブマネジメント部 疋田智)
関東大震災からわずか4年後の大惨事
以前、このサイトでお伝えした関東大震災の「リアルな様子」とは「地震の直接被害(揺れ被害)はそこまではなかった、しかし、その後の火災が最悪の結果を生んだのだ」というものでした。その経験と反省は、その後の防災に活かされたはずです。
ところが4年後に京都府北部で起きた大地震は、関東大震災とまったく異なる様相を呈しました。

昭和2(1927)年の京都府宮津町(現宮津市)で、地震は起きました。
当時の記録で震度6。しかし、当時の最大震度の設定は、震度6までしかなく、今の基準で言うと、震度7相当とされる地域も多々あったとされています。
その代表的地域が現在の京丹後市・峰山地区・野田川地区・網野地区で、これらの地域の家屋倒壊率は、ほぼ100%であることがそれを物語っています。
ひと目で分かる惨状ですが、関東大震災と何かが違います。この時点では焼け跡がありません。この地震の場合は、揺れで、一瞬のうちに町や村が壊滅したのです。


関東大震災の場合、地震の揺れではそこまで家屋は倒れませんでした。その後の東京を壊滅させたのは火災の猛威だったのです。
この揺れの差は「直下型地震」と「プレート型地震」の差だと推測されています。
一瞬にして壊れた町



奥丹後地震の震源は、京丹後市の郷村断層(長さ約18km)と、宮津市の山田断層」(長さ約7km)であるとされます。
これらの断層のズレが地中で起き、途轍もない揺れをもたらしたのです。家屋の被害は全壊1万2,584棟、半壊9,443戸、焼失8,287戸におよびました。
注目すべきは地震の直接被害の方が、火災被害よりもはるかに大きかったことです。
地震発生時刻がまだ寒い3月であり、なおかつ夕刻だったために、暖房や炊事の火を原因とする火災が数多く発生しました。しかし、それら火災による死亡者は全体の22%にとどまり、多くは壊れた家屋の下敷きになったことが死因だったと言います。
何かに似てますね。
そう、阪神淡路大震災と、今回のトルコ大地震です。いずれも断層が関わる直下型地震でした。