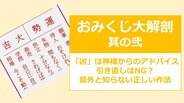町職員からの情報をもとに落札「常態化」

続いて行われた検察側による冒頭陳述で、上島町内で行われてきた公共工事の実態が読み上げられる。
「上島町では『島の工事は島の建設業者が落札する』という暗黙の了解があり、町内の建設業者の間では、談合の上であらかじめ落札業者が決められ、町職員からの情報をもとに、入札の上限価格である予定価格付近で落札することが常態化している」
「2015年から2022年7月までの上島町発注の公共工事の平均落札率は、約95%だった」
腰を掛けたまま不動の被告3人は目をつむり、時おり顔をしかめるような様子を見せながら聞き入っていた。
「町の産業建設部長(当時)のO被告(当時)は、2015年ごろから町内の建設業者に価格を教えるようになった。業者側からの依頼を受けて教えることもあった。その見返りとして、建設業者から中元や歳暮でビール券などを受け取っていた」
冒頭陳述は、今回の裁判の核心となった犯行の状況に迫る。
漁礁の設置工事について、地元建設会社XとYの間で「交互に落札する旨の談合が成立」していたとしたと指摘。
起訴されている2020年の工事では、地元建設会社Yの元役員・N被告(当時)は、町の産業建設部長(当時)のO被告(当時)から聞き出した予定価格に対して99.73%となる3120万円で落札した。
「談合」通用しづらくなり…
さらに「浮桟橋」の改修工事をめぐっても、2013年から2020年までの間に、合わせて14回の改修工事が町から発注されていたが、その多くは町内業者しか参加することのできない指名競争入札方式であったことから、同じく地元建設会社XとYが中心となって談合が行われ、落札業者が決定されていたと指摘。
しかしその後、金額の大きい工事については町外からも業者が参加できるように町の入札実施要領が変更されたことから「談合」が通用しづらくなった。
落札を望む地元建設会社Xの元役員・M被告(当時)は、町職員や町の産業建設部長(当時)のO被告(当時)に依頼して、調査基準価格をメールで入手。
その情報をもとに、調査基準価格と1円単位まで同額となる1億504万2108円で落札したという。なお、この入札が行われた時、地元建設会社Yは22円違いの1億504万2130円で応札していたとした。
「会社続けていきたい」
続いて行われた証人尋問には、地元建設会社Xの元役員・M被告(当時)の親族が出廷。
弁護士から入札妨害について聞かれると「知りませんでした」「大変なことをしたと思った」と回答。
また、M被告(当時)の人柄については「真面目に仕事をする人」とした上で「反省していると思う」「まだ会社は続けていきたい」「これまで通りに頑張って欲しい」と、思いを語った。