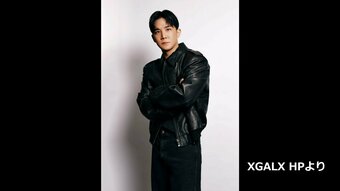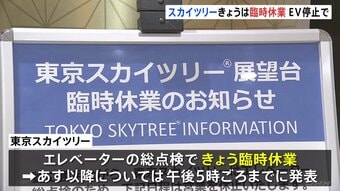北海道旭川市で去年(2021年)3月、凍死した状態で廣瀬爽彩さん(当時14歳)が見つかった問題で、今月15日、旭川市教育委員会の第三者委員会が、「いじめがあった」とする中間報告を公表した。第三者委員会は、いじめと認めなかった当時の学校などの対応を批判、爽彩さんの母親は「学校は誰が見てもいじめだと分かる状況だったのに、なぜ『いじめ』ではないと断言できたのでしょうか」とのコメントを発表した。
今回のいじめ事件でも学校側は「いじめ防止対策推進法」に則った対応ができていなかった。いじめ重大事態に至るケースを見ていると、多くの場合、学校側が法の趣旨を理解していないとしか言いようのない誤った姿勢をとり続け、“疑わしいものでも対応する”という基本的な姿勢に欠けている。
■キツキツの状態でまわすブラックな教育現場
なぜ、こう何度も何度もメディアで取り上げられて問題化しても、学校は法律を無視するのか。無視してしまうのか。または無視せざるを得ないのか。
背景にある要因の一つとして、「教員の”ブラック勤務”問題」が挙げられるだろう。一部の教員たちは多忙のあまり、“これ以上、業務を増やしたくない”と思い、いじめを見て見ぬふりをする。疑わしいものを察知しても、気づかなかったことにしてしまうのだ。
私が担当する「報道特集」では、今年(2022年)2月12日にこの問題について放送した。放送内容は、YouTubeに掲載されていて、既に60万回、視聴されている。
番組では、まず大阪府立高校の西本武史教諭が勤務校を相手どり裁判を起こしたケースを取り上げた。

ひと月の残業時間が最大で155時間と“過労死ライン”80時間の2倍近くに達し、5か月の休職を余儀なくされたという。放送後、西本教諭の適応障害は「公務上の災害」と正式に認定された。そして裁判は、今、大詰めを迎えている。これまでの裁判で学校側は「心身の不調に気づかなかった」等と主張しているが、西本教諭は当時の校長にメールで「もう限界です」などと直接、窮状を訴えていた。(大阪地裁の判決は6月28日)