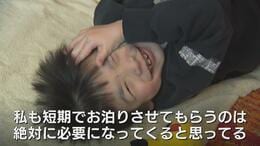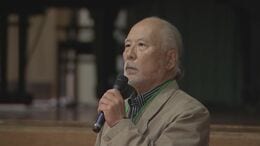「酒気帯び運転の危険性が現実化」判決は懲役5年の実刑

検察が懲役7年を求刑して迎えた、11月18日の判決。
大阪地裁(三村三緒裁判官)は、起訴事実をすべて認定。
被告側が否認していたひき逃げの罪についても、「現場が市街地の交差点の横断歩道上であることからすれば、衝突してしまった対象としてまず想定されるのは歩行者や自転車運転者であり、その現場を日常的に通っていた被告がそのことを思いつかなかったとは考えられない」「ドライブレコーダー映像で、約20秒間の停車中に当該大型トラックの前照灯が消え、ドアの開閉音がしたことも考え合わせると、被告は衝突に気づき、ギアをニュートラルに入れるなどした後、ドアを開けて何らかの確認をした、あるいは確認しようとしたと合理的に推認される」と指摘。
「人に傷害を負わせたかもしれないという未必的な認識があったと推認され、救護義務違反の故意が認められる」として、ひき逃げの罪も成立すると断じた。
そのうえで「酒気帯び運転の危険性が現実化した事故で、過失も極めて重大と評価される事案であり、態様は相当に悪質」と指弾し、落合被告に懲役5年の実刑を言い渡した。
落合被告は言い渡しをじっと聴いていた。言い渡しの前と後には、検察官側の席に一礼した。
被害男性の父親は、言い渡しの途中、ハンカチで涙をぬぐう場面があった。