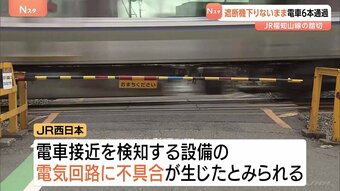昨年10月からおよそ1年間、内閣総理大臣を務めた石破茂氏の退任から1ヶ月。物価高対策、選択的夫婦別姓、戦後80年談話など在任中の取り組みと残された課題、そして退任後に急浮上した「議員定数削減」の議論や高市総理の「台湾有事」をめぐる発言など、石破前総理に在任1年と現政権の動きついて聞きました。(全2回の後編:石破氏「選択的夫婦別姓は『絶対ダメ』と言う人がいた。話がそこから先に進まない」いま振り返る在任1年と現政権の動き【インタビュー前編】から続く)
聞き手:荻上チキ(評論家・ラジオパーソナリティー)、南部広美(フリーランスアナウンサー)、澤田大樹(TBSラジオ国会担当記者)
(TBSラジオ『荻上チキ・Session』2025年11月13日放送「石破茂前総理がスタジオ生出演 政治とカネ、戦後80年所感…在任1年を問う」より)
「納税者の代表が減っていくことは、そんなに素晴らしいことですか」
――議員定数削減については? 地方創生の面から考えると、人口減の激しい地方の声がますます届きづらくなる問題をはらんでいると思います。(リスナーからの質問)
定数全体の問題、そして仮に減らすことを是とすれば、「比例区だけ減らす」という問題と、2つの議論があります。
定数を減らすべきだという話は、突き詰めると「少なければ少ないほどいい」という話になりそうです。「身を切る改革」として。しかし、主権者たる国民の代表、納税者の代表が減っていくことは、そんなに素晴らしいことですか、ということだと思います。
だからそれぞれの議員が、主権者や納税者の利益を反映して議会で議論をしているか。ちゃんと議論をしていれば、納税者の代表が少なければ少ないほどいいっていうのは議論としてなんか変だなと私は思っています。日本の国会議員の数は諸外国に比べて決して多くありません。問題は、それぞれの議員が納税者の代表としてどれだけ活動しているか、ということがもっと分かるようにすることです。
小選挙区制を導入する際に比例代表を併用させたのは、小選挙区で49対51(という接戦で)勝ったならば、49の負けた方の意見をどうするのか、ということがあったからです。これも議論がありますが、復活当選という形で議席が得られることもある。政党が議席をとったら、小選挙区の得票は少なくても当選するということになる。少数意見の反映ということで比例代表を並立させたんだけど、そのやり方でなければ少数意見は反映できませんでしたか、と。
小選挙区に変えたのはもう30年くらい前のことになっていて、当時のことを覚えてない人がいっぱいいます。「中選挙区制に戻すんだ」っていう人もいるけれど、あの中選挙区の血の雨が降るような選挙が本当に良かったですかということになるわけで。今の小選挙区の問題点はずいぶん指摘されているが、じゃあ元の中選挙区に戻しますかっていうことにはならない。中選挙区で複数人自民党が出馬するとなると、自民党同士がめちゃくちゃ仲が悪くなる。地域が分断される。もう一回あれをやりたいですか、ということです。
石破氏の画像用いたAI画像「見ていた」
――総理の時、SNSはご覧になっていましたか? 石破さんをAIで「いじる」ような動画が流布していました。
見ますよ。「へぇ、ほぉ」みたいなのがあります。私が何かに化けて歌っていたり、トランプさんやプーチンさんと一緒に歌っていたり。なかなかいろんなものがあるなと思いますが、これって使い方によっては怖いよね、と思いながら見ていました。
――AIに対するルール作りには、どういった課題を感じましたか?
AIが選挙に影響を与えているのは間違いない事実です。それが外国勢力であろうがなかろうがです。不正確な情報によって有権者の判断が変わることは、民主主義の根幹に関わることです。有権者に提供される情報は可能な限り正確でなければいけないという、当たり前のところに戻って考えなければならない。
また、AIを使って情報を流布し、労力をかけずに情報戦で戦争に勝つ、ということも可能になっていく。新しい戦い方にこれが用いられないような国際的なルールが必要です。
もう一つは、手塚治虫先生が『鉄腕アトム』のなかで昭和20年代に提唱した「ロボット法」のような、AIがいかなる役割を果たすか、どうAIを開発し、どう使うかという法的に未整備な部分がものすごくある。基本法も含めてAI社会のあり方を考える法整備はものすごく急ぐべきだと私は思っています。
「保守はイデオロギーではない。保守の本質は寛容」
――参院選中に社会に排外主義的な主張が広がったことについて、どう感じていますか?(リスナーからの質問)
排外主義になっていくということは、寛容性が失われているということだと思います。「対立と分断」よりも「協調と寛容」って、選挙のスローガンみたいだけど、世界中「対立と分断」になってしまっている。
保守の本質は寛容だと思っているんですよ。他者の意見に謙虚に耳を傾けないと、それを保守とは言わない。保守ってイデオロギーじゃないんで。保守って一種の感覚だからね。
自分と違う他者や他国を排除して優越感に浸る社会に、寛容性も発展性もないのではないでしょうか。私はそういうのは全く受け入れられません。
――戦後80年の所感は、談話にすることは難しかったのでしょうか?
戦後50年の村山談話、60年の小泉談話、70年の安倍談話は、それぞれ閣議決定を経ています。今回はかなり早い時点から「もういらない」「70年談話で済んでいる」「これ以上何を上書きするんだ」という意見がありました。出すこと自体がけしからん、と。
談話にすると閣議決定が必要で、全ての閣僚と与党の了解がいる。そうなると、各段階で「これはダメだ」「あれはダメだ」という話になるだろうと。形式とか時期ではなくて、中身なんだろうなと私は思いました。「なんで閣議決定を経なかった」ということになるんだけれど、参院選もあり、その後の政治の流れを見ていくと、そのことに議論が収斂していくのはあまり生産的ではないと思ったので、所感という形にしました。