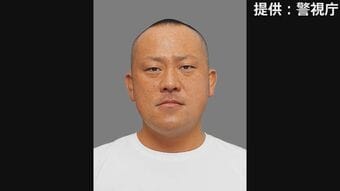「クマが来たルート 検証を」地域間で共有しないと繰り返される
皆川玲奈キャスター:
クマと共存していくためにどう対策を取ればいいのかどのように考えますか。
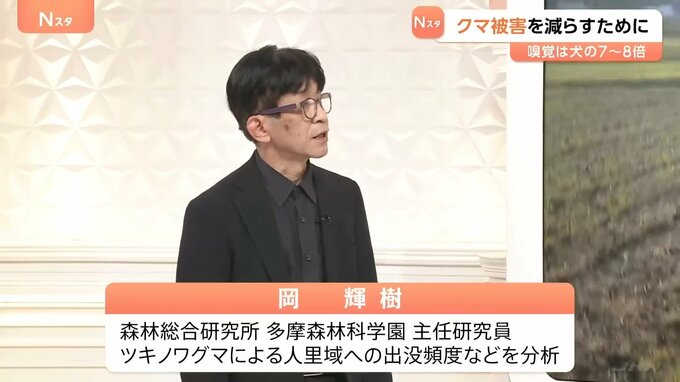
岡 主任研究員:
一度でもクマが現れた地域では、「なぜそこにクマが来たのか」、「どのルートを使ってきたのか」、「どこへ行ったのか」をきちんと分析して、障害を消していく必要があると考えます。

皆川玲奈キャスター:
“緩衝地域”を整備していくといった話もありました。その有効性はどのように見ていますか。
岡 主任研究員:
この地域では非常に成功したという例がありました。ですが、実際にはかなり難しいというのが実情ではあります。そのため、まずは排除地域をきちんと作り上げることが重要です。というのは、人が生活している圏内で誘引物を除き、隠れられそうな場所を少しでも少なくしていく。そういった新しいゾーニング管理の方法へと舵を切っていかなければいけないのかもしれないと考えます。
皆川玲奈キャスター:
となると、どういった空間を作ればいいですか。
岡 主任研究員:
まずは、地域の小さな単位でも構いませんので、隣の方と連携をとりながら、誘因物がある場所や隠れられそうな場所をなくしていく。そして、徐々に連携する単位を少しずつ大きくしていく。いずれは、“地域ぐるみ”や、さらには“街ぐるみ”でそういった管理の手法を取り入れられるようになればと考えています。
==========
<プロフィール>
岡輝樹さん
森林総合研究所 多摩森林科学園 主任研究員
ツキノワグマによる人里域への出没頻度などを分析