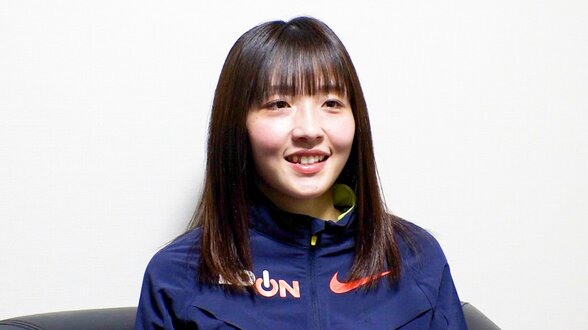34年の時を経て、偉大な歴史が再現された。予選(9月14日)で44秒44の日本新を出していた中島佑気ジョセフ(23)が、16日の男子400m準決勝3組で44秒53の2位。91年東京世界陸上の高野進以来、この種目での決勝進出を果たした。当時高野が与えたインパクトは絶大で、その後の短距離・ハードル選手たちは、世界を目指すことが当たり前の雰囲気になった。男子では400mハードル、200m、100m、110mハードルの順でファイナリストが誕生したが、きっかけを作った400mでは、高野に続く選手がなかなか現れなかった。中島はどんな走りで34年ぶりの快挙を実現したのだろう。また、高野と中島の“意外なつながり”も紹介したい。
ラスト100mで5人をゴボウ抜き
中島の“末脚”の強さが、テレビ放映を通じて日本中に知れ渡った。公式に発表されたデータで300m通過は32秒77の7位。トップを走っていたK.ジェームズ(33、グレナダ。22年オレゴン世界陸上銀メダル)とは0.81秒、約6~7mの差があったが、そこから5人を抜き去った。2位以下の7人が0.44秒差でフィニッシュする混戦だからこその逆転劇だったが、中島のラスト100mの11秒76は、3組目では一番、準決勝全体でも二番目の速さだった。
中島は「冷静」に走ったことが、逆転劇の要因だったという。「準決勝になると一か八かを狙って、前半から速いスピードで突っ込んでくる選手がいることは想定していました。それに惑わされず、(44秒44の日本新で走った)予選で良い形で走れたので、自分の感覚を信じて、自分のスタイルに徹して、最後150m、100mで勝負していこうと思っていました」。
予選と準決勝の通過タイムを比較すると100mが11秒20と11秒23、200mは21秒52と21秒65、300mが32秒69と32秒77、そして400mが44秒44と44秒53。中島自身は同じペース配分で走り切っていた。
大会前には高野の34年前の偉業について、「決勝に行って初めて、偉大な高野先生に少し肩を並べられます。今の世界陸上でもう一度、違う選手が400mの決勝に行くことに価値があると思うので、しっかり受け継いでいきたい」と話していた。
準決勝レース後に高野について質問されると、「感慨深いですね」とコメント。「自分はオレゴン世界陸上、パリ五輪と(個人種目は)不甲斐ない結果に終わっていました。東京世界陸上は皆さんの声援を力に変えて、自分のバリアを破る絶好の機会だと思っていたんです。地元開催の世界陸上は最初で最後のチャンス。このチャンスを逃さず目標を達成できたことは本当に幸せですね」
中島の終盤の強さは以前から注目されていた。学生時代から指導する東洋大の梶原道明監督(72)は、中島の特徴をこう話した。
「スピードがすごくある選手ではありませんが、マックスより少し下のスピードで繰り返す能力が高かったんです。代表になり始めてM.ノーマン(27、米国。オレゴン世界陸上金メダル)のチームで500m+400m+300mの練習をやったときも、最後の300mはジョセフの方が強いこともありました」
国内では終盤の強さで勝つことはできても、世界では前半で後れないことが重要と考え、ここ数年は前半のスピードアップに取り組んできた。しかしそこを重視するあまり、国際大会で終盤のスピードが落ちてしまっていた。45秒04と当時の自己新で走ったブダペスト世界陸上準決勝では、200m通過は21秒56と今回と変わらないが、最後の100mは12秒10かかっていた。
今季は終盤の強さを軸にレース構成を考える方向に変更した。前半をより楽にスピードを出すことを意識し、結果的に今大会では同レベルのタイムで200mを通過できた。一度、前半のスピード向上に取り組んだことが、今回の44秒4~5台の連発につながっている。