「巨大地震警戒」への対応 津波被害が想定されていない地域でも地震への備えは必要
特に問題となるのが「巨大地震警戒」への対応です。

発表された場合、自治体が津波に備えて事前に避難を求める住民が約52万人にのぼることが内閣府の調査で明らかになりました。(福岡・佐賀はゼロ)
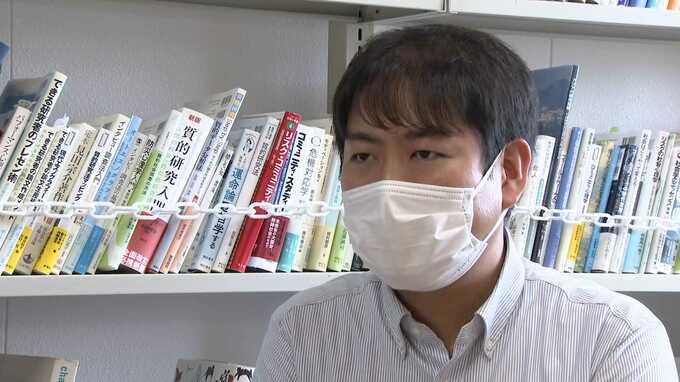
九州大学・杉山高志 准教授
「仮にもし事前避難するならばどこに避難すればいいのか、あるいは避難したとしても、その後どうやって1週間程度の避難生活を継続すればよかったのか等々ですね。命を守るだけではなくて、命を繋ぐための資機材がいかに準備不足なのかということも露呈いたしました」
南海トラフ巨大地震をめぐっては、今年3月国が発表した新たな被害想定で福岡県内の津波による死者が最大200人と大幅に増加しました。

津波の想定区域が広がった北九州市は、8月津波から避難する際の参考となる海抜表示を増設しました。
津波による被害が想定されていない地域でも地震への備えは必要だと杉山准教授は強調します。

九州大学・杉山高志 准教授
「沿岸部の方だけではなくて中山間部の方も甚大な被害を受けます。例えば能登半島地震の時にもマグニチュード7くらいの地震でしたが、中山間域では多数の土砂災害が生じたために、孤立状態が生じました。当然福岡や佐賀や大分といった中山間域でも十分起きうるものです」

最悪の場合、死者がおよそ30万人にのぼると試算されている南海トラフ巨大地震。

防災対策の重要性を広く理解してもらうために制定された「防災の日」に、改めて備えを見直す必要がありそうです。














