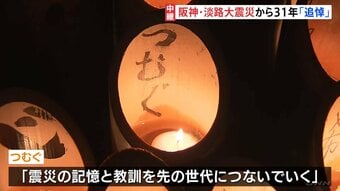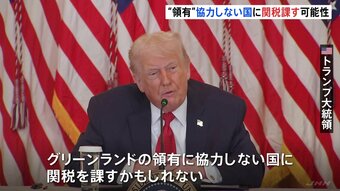戦争の記憶を伝えるには「知識」に加え「感性」が必要
編集部 さて、「サンデーモーニング」でもたびたび戦争についても伝えられてきましたし、毎年8月、戦争に関する特番を司会者として何度も出されています。今、振り返って、戦争関連のニュースで心に残ること、あるいはエピソードはありますか。
関口 それはもうね言い出したらキリがないぐらい。やっぱりテレビの 1つの使命としてね、戦争というものを伝えていくべきだというのが私の考えだし、また、そうあるべきだよね、メディアっていうものは。
だから、いろんな証言者の話聞いたしね。それから広島・長崎ももちろん行って、沖縄も行ってるしね。だから、これがちょうど今年が戦後 80年でしょう。だから、戦争を語るというか、戦争体験者がもうほとんどいなくなってきたこの時代、これからどうやって戦争をテレビっていうものが伝えていくべきかというのは、非常に難しいところへ来たなぁという感じがしている。
私は、いろんな戦争特集の番組でやらせてもらったけど、本当に、体験者から聞く話っていうのはインパクト強いよね。体験なさったわけだから。で、そういうことがこれからはだんだん少なくなるとするなら、戦争というものをメディアがどう伝えてっていいのか、どんどん難しくなるんじゃないかなって心配してる。
編集部 確かに時間が経てば経つほど、皆さん亡くなられていくわけですからね。
関口 私はね、戦争を伝えるっていうことは、どっか知識、と感性っていうのかな、が伝わらないと、何か中途半端なものになってしまうっていうのかな、知識だけでもね、戦争って分かったことにならないと思う。
やっぱり、そこに感性、「ああ、そんな惨いことをしたんだ」とか、「それは人間としてやっちゃいけないよな」っていう、なんかそういう感性に訴える部分が僕は必要だと思うんでね。それが戦争体験者の話を聞いていると両方あるわけですよ。知識も教えてもらえるし、それからなんか感性に訴えられるものもあるわけだよ。
だけど、その伝え手がいなくなると、その感性を訴えるっていうか、感性を伝えるところが非常に手薄になっちゃうっていうか。知識はね、本を読めばいくらでも、いろんなことは書いてあるから、どうにかなるんだけど。そこを心配してるんですよ。
編集部 歴史の教訓を忘れると、また同じ失敗を繰り返しかねない。
関口 はい。今でもジャーナリスティックな人たちとの付き合いはあるんだけど、そういう人たちと 一杯飲んでても、やっぱり「また世の中がちょっとおかしくなってるぞ」っていう話はする。私も「なんか大丈夫かな」っていう心配をしている。

編集部 戦後80年になりますが、世界ではウクライナやガザとかとか、もう非常に心が痛む映像がどんどん入ってきていますけれども、関口さんは今の世界をご覧になって、どんなことを思われますか。
関口 決していい方向に世界は進んでないような気がしてますよ。何かバラバラというか。それからやっぱり自分の利益が一番っていうね、考え方が強くなってきてるような気がして。それは揉め事の元だよね。やっぱり何か譲り合うとか、相手の気持ちがわかるとか、そういうものがあって、平和なり調和なりがあるんだろうと思うけど、自分たちが一番でなきゃいかんという考え方は、それは危ないなと思ってる。