失敗は最高のワクワクの種。次につながる「良質な失敗」をどう設計するか

「子どもの創造力を育むポイントは、いい感じの裏切りです。」正頭さんは、子どもの予想を少しだけ外すことで、「え、なんで?」という知的好奇心、つまり最高のワクワクの種が自然と生まれると語る。予期せぬ出来事が引っかかりとなり、「次こそは」と、人を夢中にさせていく。
アプリだけでなく、子どもたちの学び体験のワークショップ等も開催している中村さんは、子どもたちが何度も挑戦したくなる仕掛けをUXデザインに落とし込む工夫をしていると話す。例えば、子どもの答えが間違えていたときに、単に「バツ」を表示したり「ブー」という音で示すのでなく、クスッと笑えるような演出にすることで、子どもたちに「間違えることは怖くない」という前向きなメッセージを印象付けられるという。「考えていたのと違った」という体験を失敗ではなく、ポジティブに受け止められる体験にすることこそが、探究心につながるという。一方で、実際の学校教育の現場では「良質な失敗」をさせることが難しい現実もある、と正頭さんは指摘する。
「学校は、生徒に失敗させてはいけない、というのがベースにある。そのために細心の注意を払って教育を進めている。その中で、卒業生に『学校は、失敗を経験できない場所だった』と言われたことが深く心に残っている」
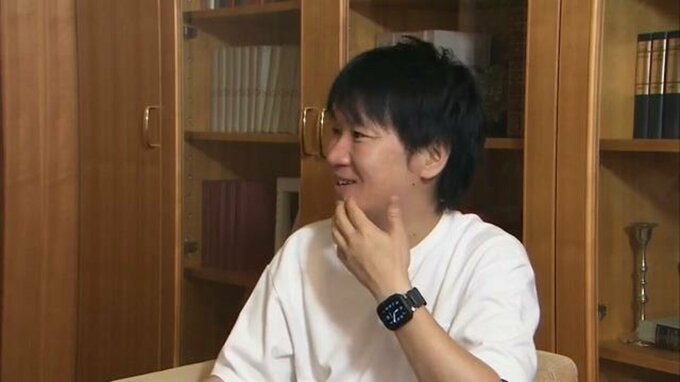
では、「良質な失敗」とは何か。伊藤さんは、「面白いゲーム」と「つまらないゲーム」の分かれ目は「負けた理由が分かるかどうか」だと解説する。理由が分からなければ「ああすればよかった」などの次に向けての考察が生まれず、そこで終わってしまう。しかし、理由が分かれば「次はこうしよう」と工夫が生まれ、もう一度挑戦したくなる。教育においても、次に繋がるヒントを含んだ「良質な失敗」を設計することが、子どもの学びを深める上で不可欠だと語った。
エデュテインメントは、「エデュケーション」と「エンターテイメント」のかけ合わせだが、決して「学びを“エンタメ風”にすること」ではない。エンタメの力で、子どもの本質的な興味を引き出し、子どもがワクワクしながら、自ら考えて挑戦する姿勢を育むことであり、第一線の経営者たちが語る子どもの心を掴む設計の秘訣は、これからの「学びの形」を変えていく大きなカギとなるだろう。














