「推し」と「制限」が学びのエンジンに。子どもの心を掴む設計の妙
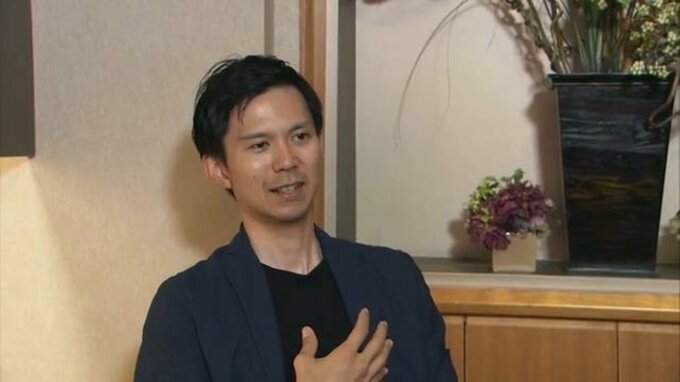
では、子どもの心を掴むにはどうするのか?現役教諭の正頭さんは、コンテンツ設計にも工夫が求められるという。例えば、現代の子どもたちに根付く「推し文化」。「推しがいないと落ち着かない」という感覚が小学生にもあり、子ども自身が自分で選べるキャラクターを用意することがエンゲージメントにつながると分析する。伊藤さんも、開発に携わった金融教育アプリで、当初はキャラクターを1体しか用意していなかったが、子どもたちからの「キャラクターがもっとたくさん欲しい」という声を受け、キャラクターの数を増やした経験を持つ。ユーザーである子どもの反応を見ながらサービスを設計することが、子どもの心を掴むことに繋がるという。
子どもの心を掴むカギは「推し」だけではない。もう一つのカギは「制限」だ。子どもに「1時間後にまた遊べる」といった時間制限を設けることで、デバイスに触れていない時間もコンテンツについて考えさせ、ワクワク感を醸成する。中村さんが自社で展開する知育アプリ「Think!Think!」では、子どもの利用がより柔軟になるよう、あえて「1日3プレイ」から「週21プレイ」へと制限を変更。この変更で、子ども自身が1週間の使い方を戦略的に考えるようになり、「プレイに集中し、夢中になる時間を過ごしてほしい」という狙いが達成されたという。こうした「適切な制限」は、俳句の「5-7-5」のように、子どもの創造性を制限するのではなく、むしろ刺激すると現役教諭の正頭さんは指摘する。














