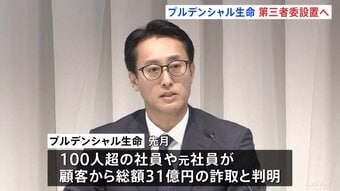捜査着手の「順番入れ替え」
1998年2月、大蔵キャリア官僚の証拠はほぼ固まり、捜査着手に向けての準備は整いつつあった。
東京地検検事正の石川は、かつて定期的に昼食を共にしていた同期の法務省刑事局長・原田や、疑惑が取り沙汰されていた大蔵省審議官・杉井孝らとの会合を、特捜部の接待汚職捜査が本格化するのにあわせて、取り止めたという。
一方、水面下では特命班の粂原研二(32期)らが、大蔵省OBの国会議員に関する捜査を進めていた。
捜査対象となったのは大蔵省出身の新井将敬衆議院議員。株取引をめぐって日興証券に利益要求の疑いが持たれていた。
戦後の東京地検特捜部が手掛けた多くの疑獄事件では、しばしば「最終ターゲット」として国会議員を立件し、捜査を終結させるスタイルが多かった。
熊﨑ら特捜部は、現職の大蔵キャリアに着手したのち、仕上げとして新井将敬を立件し、一連の大蔵省接待汚職事件を着地させる方針で捜査を進めていた。
一方で、筆者のもとにはこんな情報が伝わってきていた。
「法務省が『新井事件を先に着手してくれ』と検察に要請してきたようだ。どうやら捜査の順番が入れ替わったらしい。法務省は政治家ルートの新井事件に世間の注目を集め、特捜部には大蔵キャリアをやらせないつもりかも知れない」
特捜部は1月26日に大蔵省の強制捜査に着手し、まずノンキャリアの金融検査官を摘発していた。
関係者によると、実はその直後、法務省幹部から検察首脳に対して「大蔵省汚職捜査は3月末をもって終結する」との意向が示された節があった。
ある検察関係者は当時をこう振り返る。
「国会議員の新井を立件すれば、当然ながら世間の関心はそこに集中する。特捜部も新井ルートの捜査に人員を割かれ、手間もかかる。そうなると後回しにした『大蔵キャリア』の摘発は「3月一杯」という期限を考えると“時間切れ”でうやむやとなる。立件不可能となる。法務省は、そこまで考えたのではないか」
法務省幹部の「順番入れ替え」の要請に対して、特捜部長の熊﨑は「やはり新井は最後にしたい」と検察首脳を通じて反対したというが、最終的には受け入れた。
つまり、法務省は「大蔵キャリアの摘発」に消極的だった。
ノンキャリアの金融管理官の自殺に加え、その前には第一勧銀の元会長が総会屋への利益提供事件の捜査中に自殺するなど、相次ぐ事件関係者の自殺に神経をとがらせていた。
大蔵省と向き合っていた法務省は、大蔵省との関係をこれ以上、悪化させることは避けたかったのだ。
要するに、法務省としては特捜部が「国会議員の新井将敬を立件すれば時間切れとなり、特捜部は大蔵キャリア摘発には執着しないだろう」との打算があったと見られる。
そうした構図の中で、法務省は検事総長の土肥、東京地検検事正の石川を説得し、「大蔵キャリアルート」と「新井将敬ルート」の捜査の順番を入れ替えるよう要請したのである。
そして検察首脳の意向を受けた特捜部は、まず新井将敬事件の強制捜査に踏み切った。
しかし、この判断の先には、誰も予想しなかった事態が待ち受けていたーー。
(つづく)
TBSテレビ情報制作局兼報道局
ゼネラルプロデューサー
岩花 光
《参考文献》
村山 治「市場検察」 文藝春秋、2008年
村山 治「特捜検察vs金融権力」朝日新聞社、2007年
村串栄一「検察秘録」光文社、2002年
読売新聞社会部「会長はなぜ自殺したか」 新潮社、1998年
産経新聞金融犯罪取材班 「呪縛は解かれたか」角川書店、1999年
熊﨑勝彦/鎌田靖「平成重大事件の深層」中公新書ラクレ、2020年
伊藤博敏「黒幕 裏社会の案内人」小学館、2014年