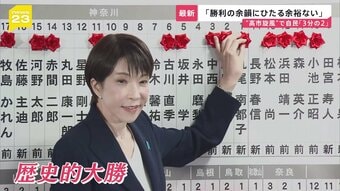「つけ回し」と「応報性」
Mとともに、金融検査部管理課長補佐のTも逮捕された。Tは三和銀行や北海道拓殖銀行などから、飲食・土産・観劇など約「450万円」相当の接待を受けていた。
三和銀行には「ミスターMOF担」と呼ばれ、将来の社長候補と言われたHがいたが、Hらは当初「やられるのは第一勧銀が中心だろう」と見ていた。
しかし、三和銀行はあろうことか、大蔵省が東洋信託銀行に対して実施したときの「検査報告書」のコピーをTからひそかに入手していたことが発覚する。
この報告書は「示達書」と呼ばれ、検査対象の銀行の経営状態について詳細に指摘した“極秘文書”であり、漏れることはあってはならないことだった。
また三和銀行はTから飲食店“つけ回し”の請求書を受け取って負担していたほか、Tが知人女性と会食した際にも高級料亭を予約して費用を払っていたことなども明らかになった。
Tが北海道拓殖銀行から接待を受けたのは、大蔵省から拓銀に天下っていた元金融検査官と、検査官OB会「霞桜会」で知り合ったことがきっかけだった。
このOB会は、金融検査部に所属した経験のある元職員の集まりで、毎年2回、都内にある大蔵省の施設で会合を開いており、現職では唯一、Tが世話人を務めていたという。
特捜部の捜査により、MとTに対して接待攻勢をかけていたのは、第一勧業銀行、三和銀行、あさひ銀行、北海道拓殖銀行にとどまらず、東京三菱銀行と住友銀行に及んでいたことも判明する。
Tが好んで要求していたという「ダンスショー」が楽しむことができる「フラメンコレストラン」での接待も含まれていた。
本来、公平かつ中立であるべき大蔵省の金融検査は、MOF担との「ズブズブの癒着関係」によって骨抜きにされていたのだ。バブル崩壊後の金融機関が抱える不良債権処理の先送りの要因にもなった。
とくにMが第一勧銀から総会屋・小池隆一への融資を見逃していたことにより、第一勧銀はその後も100億円近い不正融資を続け、小池の株取引の資金源となった。
小池に対する不正融資を放置したことは、総会屋事件の拡大につながったのである。
東京地検特捜部はそうした「接待」のうち、どのようなケースを収賄罪で立件しようとしたのか、その「判断基準」は何だったのだろうかーー。
熊﨑特捜部長、山本副部長、大鶴班長らが「摘発価値」があるとして、最も重視したのは、「つけ回し」と「応報性」の2点だった。
つまり、「つけ回し」は前にも触れた通り、大蔵官僚が身内だけで飲食した代金を、銀行側に負担させる行為のことだ。
もう一つの「応報性」とは、行為自体の悪質性である。やってはならない違法行為、漏らしてはならない「秘密情報」を、接待の見返りとして実際に漏洩していたかどうかである。
すなわち、「抜き打ち」であるべき検査日程や対象支店という機密事項をMOF担に漏洩した「金融検査官ルート」の捜査は、まさにその「判断基準」に合致していたのだ。
アンタッチャブルとされてきた「官庁の中の官庁」大蔵省への強制捜査は、霞が関にも激震を与えた。強制捜査着手当日の1995年1月26日、三塚博大蔵大臣は辞任に追い込まれた。
また、この日はちょうど「30兆円の公的資金を投入する法案」が国会で審議中だったこともあり、永田町にも激震が走った。
国会議員からは「法案審議中に強制捜査に着手するのは検察ファッショだ」との常套句で、怒りの声が上がった。
このとき、法務省官房長として国会対応にあたっていたのが、但木敬一(21期)だった。
そして、大蔵省との連絡窓口になっていたのが、法務省刑事局長の原田明夫(17期)である。
但木と原田はともに赤レンガ派の「法務官僚」として、政府や大蔵省側の意向を汲みながら対応にあたっていた。
一方で、検察現場を率いるトップの検事総長の土肥孝治や、特捜部を統括する東京地検検事正の石川達紘らは「接待によって金融行政を歪められたという証拠があるなら、やらない理由はない」としていた。
しかし、法務省と検察現場には、次第に捜査の方針をめぐって温度差と軋轢が生じていくーー。