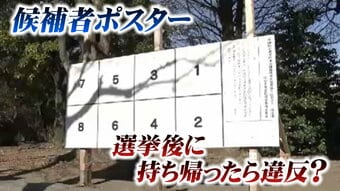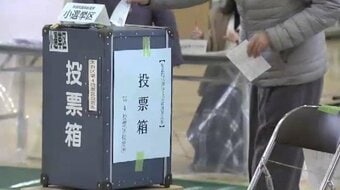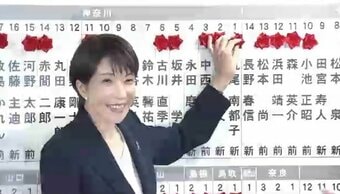正しく観測できないケースとは?
2011年3月11日の東日本大震災。沿岸部が大津波に襲われ宮城県石巻市鮎川の津波計は建屋の窓ガラスが壊されて装置も破壊されました。当時の観測データについて、津波工学が専門の東北大学、今村文彦教授に説明してもらいました。

東北大学 今村文彦教授:
「第一波はとらえていたんですけど、この時には検潮所は大丈夫だったんですね。その後さらに大きな津波が来まして破壊されてしまいました。ですので、そのあとデータなしという状況で、もっと大きな津波が来ていたんですけども、情報としては出せなかったわけです」

去年1月1日に発生した能登半島地震でも津波計による観測ができなくなりました。
気象庁 鎌谷紀子地震津波監視課長(当時):
「今の段階ではデータが届いていないということしか分かっていません」

石川県の輪島港の津波計では、地震の直後に1.2メートル以上の津波を観測した後、正しいデータがとれなくなりました。また、珠洲市長橋の津波計でもデータが入らなくなりました。その後の調査で、この2か所は海底が隆起するなどして正しい観測ができなくなっていたことが分かりました。