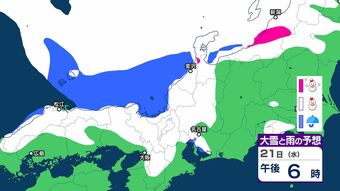視覚障害者にスマホの使い方を無料で指導
今回は東京都盲人福祉協会が行なっている視覚障害者のスマートフォン訓練事業を取材しました。
スマートフォン、いわゆるスマホは今では電話やメール以外にも買い物の支払いから医療や災害の情報収集まで日常生活に欠かせないものになりました。
見える人にとってはとても使いやすい機械ですが、視覚障害のある人はスマホの使用を苦手にしている場合があります。
画面に画像で表示されるアプリやボタンがよく見えない人もいるからです。
しかし、視覚障害者がまったくスマホを使えないわけではありません。
スマホのうち、iPhoneにはボイスオーバー、Androidにはトークバックという画面の様子を音声で読み上げて専用の指遣いで操作する機能や、画面拡大、画面の配色変更などの見やすさを向上させる機能といった、見えにくい人向けの補助機能が、最初から組み込まれています。
その機能と健常者もよく使用する音声アシスタント(SiriやGoogleアシスタント)を組み合わせれば、見えなくてもある程度操作ができます。
ただ高齢になって失明した人などの中には、そうした情報をよく知らない人もいます。
また視覚障害者を支援するアプリもたくさん開発され配布されていますが、操作方法を理解して、自分ひとりで使いこなせるようになる人ばかりではありません。
そうしたことへの対応として、東京都盲人福祉協会は、都の補助金で行われている訪問訓練(歩行訓練、生活訓練、点字訓練など)のひとつとして、当事者の自宅を訪問してスマホの使い方を無料で指導しています。
協会の生活訓練指導員で、本人も弱視の視覚障害がある白井夕子さんに事業を始める経緯を聞きました。

(東京都盲人福祉協会・生活訓練指導員の白井夕子さん)
「IT社会と言われるようになって、そこに置いてかれてはいけないっていうことで、スマホを教える人が必要になって、2016年から始まりました。いくつかアプリがあるので、その人が操作をどのぐらいできるか、 画面をいかに触って動かすことができるかっていうところに合わせて、その人がやりやすいアプリを選んでいくんですけど、画面上の操作がうまくなかったりとか、手数が多いと覚えるのがむずかしい方の場合だったら、なるべく手数が少なくてすむものにしたり、その人がやりやすいアプリを覚えていただく形をとっています。」
白井さんは2016年からこれまで約300人の当事者に訓練をしてきたそうです。
現在、同協会には白井さんのほかにもう1名、スマホ指導員が在籍しています。
白井さんによれば、もともと機械好きだったり、仕事でスマホを使っていた人などが中途失明したような場合、独力でアプリ操作を覚えることもあるそうですが、スマホそのものになじんでいなかった高齢世代の中途失明者も多いので、指導員が操作法を教える取り組みもとても大切だそうです。