■“失格者”から「調査報道」へ
ーー調査報道とはどういうものなのですか?定義はいろいろありますが、自分が取材したことを、自分の責任で報道することです。本来取材は全てそうなんですが、真実かどうかの根拠については、発表に依っていることが多いです。例えば政府が発表したから、企業が発表したから、真実として報道するという形です。調査報道というのは、ある事象が真実だということを、自分が調べて、自分の責任で、報道することになります。
ーー村瀬さんはなぜ調査報道に携わるようになったのですか?
入社してすぐ社会部に所属し、警視庁二課(贈収賄、振り込め詐欺をはじめとする詐欺、横領、背任などの「知能犯捜査」)を担当することになりました。正直言うと、本来の業務としては失格者でした。警視庁の捜査官と仲良くなって、当局に対して取材することを期待されていましたが、これには相当な人間力が必要です。そういう能力が私は劣っていて、警視庁二課の捜査官への取材はうまくいきませんでした。
私が二課担当の記者として生き残る道は、当局取材が駄目だったら、民間側への取材で頑張るということでした。これが、やってみると本当に面白かったんです。いろんな不正とか、世の中で起きている顕在化されていない疑問、裏社会で何が起きているか、まだ捜査機関は気づいていないけれども、これは大問題だよねっていう話がきたりするんです。
捜査は行われていないけれど、自分はこれは問題だと思うから取材する。当局への取材に依れないから始めた取材方法でしたが、結果当局の発表ではなく、自分の責任で取材して放送する、私の調査報道の一歩になりました。
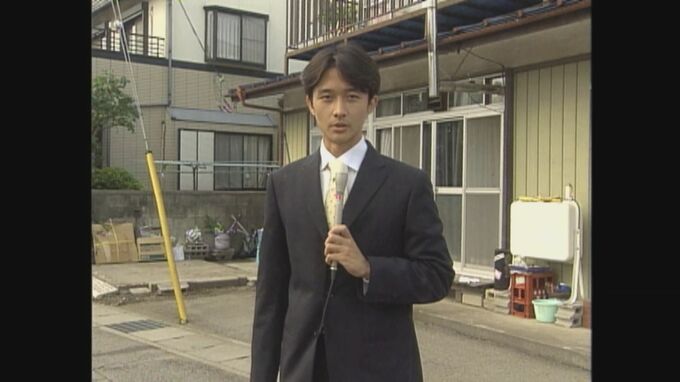
■「自分が訴えられる」ことも内部情報で把握
ーー自分の取材で、自分の責任で報道する。かっこいいですが、どこに潜んでいるかわからない問題を探して、自分で裏付けして、真実だと報道するって、大変そうですね。手間も、コストも、リスクも大きいです。実は、私は入社2年目で訴えられました。
「ある会社がかなり怪しいんだ。だから取材した方がいいよ」という情報提供があったんです。それは携帯電話かけ放題サービスを提供するとしていた会社についてでした。取材を進めると、かけ放題サービスを打ち上げて親会社の株価を持ち上げることを目的とした風説の流布事件だったんです。結局、かけ放題は“嘘”という調査報道をしました。
そうしたら、その会社から訴えられたんです。
ーーびっくりしたんじゃないですか?
実は、自分が訴えられることも内部情報でリアルタイムで把握していました。でも事前情報があったとしてもこればっかりはどうにもならなくて、入社2年目でいろんな意味で針のむしろに座らされ、大変な経験になりました。この苦労は、当事者にならないとわからなかったと思います。
最終的には、特捜部がこの会社の株価操縦を事件にして、私たちも裁判に勝ったのですが、いくら正しくても訴えられたらこういう状況になるんだということを2年目という早い段階で知れたことが今となってはよかったと思っています。
ーー大変だから調査報道を「やめよう」ではなく「よかった」と思ったんですか?
自分が取材しなかったら問題が社会の明るみに出なかったという感覚があって、個人的な満足感になってしまうかもしれませんが、調査報道をやめたいとは思いませんでした。むしろ一貫して「やりたいことは調査報道」といい続けてきました。
訴えられてよかったというのは、調査報道の在り方についていろいろ学べたからです。当局の発表に依らないで自分の責任で取材し報道するので、常に訴えられる可能性は十分にあるし、相手は訴える自由があります。その時に、法廷に出せる証拠は何かということが具体的に突きつけられます。その後の調査報道では、訴えられたらどの取材結果を証拠として法廷に出せるかなっていうのは常に考えるようになりました。
実は取材では、「法廷で証言してください」とお願いするわけにいかない協力者がほとんどなので、そうした協力者の証言や資料を除いても真実性を法廷で証明できるか、そのためには何が必要か、そんなスキルが備わっていったと思います。



















