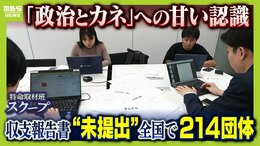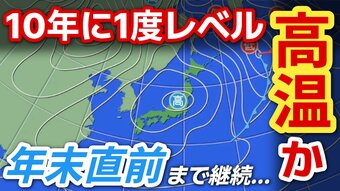災害関連死を含めて、広島県内で150人を超える人が亡くなった西日本豪雨の発生から、6日で7年でした。時間の経過とともに、災害の記憶も薄れる中で、被災地には、教訓をつなごうとする人たちがいました。
坂町の自然災害伝承公園には、献花台が設置されていました。遺族や地域住民らが花を供えに訪れていました。当時、土石流は町の大半を飲み込みました。坂町では21人が犠牲になっていて、小屋浦地区ではいまも1人の行方が分かっていません。
母と叔母を亡くした水尻忠道さんは「昔ほどはないが、今もフラッシュバックするときがある」と話しました。一方、防災教育も行っていて「小学校の子どもたちには、『このことを覚えておいてね』と。これは中学校、高校、大学で、あなたたちが家族を持ったら家族を助けるために役立ててください、と伝えている」と話しました。
政本治さん(64)は、7年前、母・朝子さんと姉・典子さんを亡くしました。政本治さんは「あっという間の7年だった」と振り返ります。
三登文恵さんが勤めていた町で唯一の保育園は、災害で大きな被害を受けました。家族は全員無事だったものの、自宅は全壊しました。
三登さんは当時、1階の屋根近くまで土砂が来ていてその上を水が我が家を通って流れるような状況で、その周りに車が、家と家の間に車が入り込んだりとかそういった状況でした」と話していました。
6日は災害の教訓を繋いでいくため、献花に孫と訪れたといいます。孫とは「波がきたらどこに逃げる?」などと話していました。「こんなことがあった。だからどうしたらいいかな?と考える、きっかけを作らせてもらう良い1日になるかな」と話した三登さんは、献花した後、孫たちに当時の小屋浦の映像を見せながら、災害について伝えました。
「ばあばの家ここよ、ばあばの家(当時は)何もないんよ。」
孫たちは真剣な目を向けていました。
三登さんは伝えようと思った理由について、「そういえば今まで、孫たちが小さいと思っていたから、伝えてなかった部分があった」と話しました。映像を見ると「忘れていたわけじゃないけど、改めてあんなことがあった…すごいことがあったんだなと思って」「当時は息子だけだったが、今は孫たちもいるので、早めに避難して守らないと」と改めて考えることがあります。
小屋浦地区にあるお好み焼き店「福水」の福井昌子さんです。当時は寝ていましたが、家のなかにも水が入ってきました。店の中のものも、何もかもが流されてしまいましたが、その中で唯一残ったのが鉄板でした。
福井昌子さんは「鉄板があったからがんばろうかねと思った」と振り返りました。さらに、「今は幸せ。大きな川に家や人や動物が流れるなんて本当に地獄だった」としました。
夕日が落ちてきたころ、灯籠およそ600個が「7.6」の形に並べられました。孫と参加していた女性は「孫たちが元気に大きくなってくれてるのは嬉しい。しかし、(発災当時は)小屋浦が小屋浦じゃなくなった。(当時は街灯も流され)真っ暗でしたからね。風化させてはいけないことが小屋浦にもあるんだなという感じがする」と話しました。
中学生たちは、できることをやってみようと、かつて通っていた、小学校の校長たちに、自分が知った災害の被害について説明していました。画像を見せながら「朝起きたらこんな状態になってたみたい」などと話して説明していました。
母校の小学校の校長は「記憶が刻まれてるから、情熱を持って防災意識を高めるために活動してくれてたんだなと改めて思いました」と話していた。