アクション映画の定番「ラスト・ミニッツ・レスキュー」
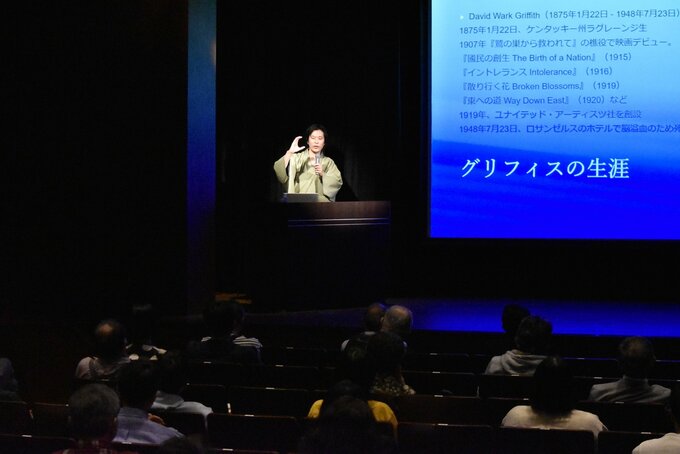
片岡さんの解説をお聞きください。
片岡一郎さん:今の我々でしたら、物語が進んでいって、それが突然過去に戻る「過去回想」は当たり前ですし、次の場面に行く時に、全然違う空間だったり、違う時間に行ったりすることも当たり前に受け入れられるんですけども、当時は「分かりづらい」と批判されました。ところが、グリフィスは「そうやることによって、映画らしい表現になるんだ」と主張したわけです。「映画でしかできない表現」を生み出して、今なら当たり前の様々な撮影技法を次から次へと誕生させて、定着させていったということで、「映画の父」と呼ばれるようになっていくわけです。
片岡一郎さん:ことに、グリフィスお得意の演出「クロスカッティング」。様々なパートを映していく中で、「ラスト・ミニッツ・レスキュー」という、グリフィスお得意の演出があります。これからご覧いただく『イントレランス』でも、その演出が使われています。
片岡一郎さん:簡単に言いますと、例えばヒロインが捕まっている。殺されそうである。悪役が迫ってくる。そして、そこに助けに行こうとする人が!パッと場面が移って、車が走って向かっていく。そうするとまたパッと画面が移り変わって、悪役がさらに迫って銃口を突きつける。ギャーという表情のヒロインが映る。そうしたらまたグーッと車が近寄ってくる。「もうどう考えても間に合わないじゃないか、どうするんだろ、どうするんだろ?!」で、パパッと画面が移っていって、「もうだめだ!」と思った瞬間に主人公がバーンと駆け込んできて、「助かった!」「間に合った!」。最後の1分1秒でようやく間に合った、という映像的な演出であっち行ったりこっち行ったりするからこそ、刺激的なんですね。
片岡一郎さん:舞台・演劇、あるいは本当に物語が時間通りに進んでいく演出でしたら、遠くから来るのが分かるわけじゃないですか。「あ、このくらいの距離だから、ということは、このくらいの時間には到着するよね、だったらこれは間に合うよね」となるわけですが、それが映画らしい演出によって「間に合うのかな?!」「どうなのかな?!」「いや間に合わないかもしれない」。映画だから間に合うに決まっているんだけども、「でもこれは間に合わない、どうしよう、どうしよう?!」という演出が可能になった。これもグリフィスの功績です。
映画『イントレランス』を監督したD・W・グリフィスが「映画の父」と言われているのは、こういった編集効果を独自にどんどん編み出したからです。














