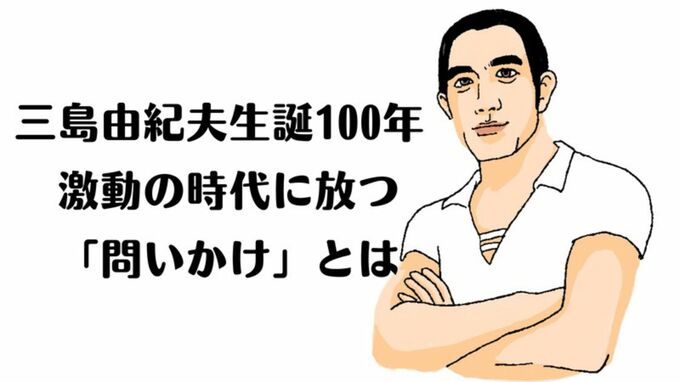2025年は戦後日本を代表する作家の一人、三島由紀夫が生まれてから100年という節目の年。著書の復刊やイベントなどが各地で行われています。この「三島由紀夫 生誕100年」をどう受け止め、またどんな意義があるのかについて、6月20日放送のRKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演した、ジャーナリストで毎日新聞出版社長の山本修司さんがコメントしました。
「生誕100年」の意義と背景
5年前には「没後50年」があり、今年「生誕100年」。三島由紀夫についてさまざまなイベントを催すには、少し近すぎるのではないか、とある人から言われたことがあります。しかし、「没後50年」の2020年はコロナ禍まっただ中で、実際には大々的に催しを行う雰囲気ではなかったことを思い起こします。
だからというわけではありませんが、今年は昭和元年から100年目ということ、つまり三島の満年齢と昭和の歩みが一致し、三島の人生が昭和と併走したということもあり、また後に触れますがこの5年で世界が様変わりしたこともあり、ここで三島文学を、また三島という人間を振り返ってみよう、改めて捉え直してみようという動きが、文学界や出版界で出ています。
没後50年にあたる2020年3月20日には、『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』というドキュメンタリー映画が公開され、私も見に行きました。その数日後に緊急事態宣言が発令されて上映が中止になったため、「早く観ておいてよかった」と思ったことをよく覚えています。
この映画は、1969年(昭和44年)5月13日に、東京大学駒場キャンパス900番教室で行われた三島由紀夫と東大全共闘の討論会を中心にしたもので、唯一中に入って取材していたTBSが撮影したフィルムを高精細映像として復元し、さらに芥正彦さんら元東大全共闘の錚々たる論客たちや、三島を研究して本にした平野啓一郎さんらに新たに取材したものでした。そのエネルギーのすごさ、豊かな知性、議論に圧倒されました。
その後の5年間には様々なことがありましたが、三島周辺での大きなことは、傑作の一つとされる長編小説『金閣寺』について、三島が原題を『人間病』などと構想していたことを示す編集者への手紙が昨年12月に見つかったことです。
この手紙は、文芸雑誌の『新潮』での連載が始まる前年の1955年6月に編集者に宛てて書かれたものとみられます。この中で小説のテーマについて「題は『人間病』(人間存在といふ病気の治療法について)あるひは『人間病院』といふのです」などと記していました。
『金閣寺』は実際に起きた放火事件を題材に、吃音によるコンプレックスを抱えつつも、金閣寺の美しさにとりつかれた芸術家である学僧の複雑な心理を描いた作品です。ここには「病を抱える存在である人間は、その病を芸術によって癒すことができるのか、また病を癒すことは人間にとって幸せなのか」という、深く簡単には理解できないテーマがあったということです。こんなことを手紙から窺うことができたわけで、生誕100年を前に大発見があったといえます。