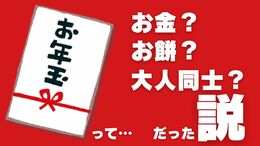戦争を終わらせるには
戦争を終わらせるためには何が必要なのでしょうか。
越智さんは「武力紛争をどこまでやっていいのかについては実は明確なルールがある」と語ります。国際法上、自衛を理由に武力行使を行う場合、「受けた武力攻撃を防ぐために必要な範囲に限られる」と定められています。「ただどこまでが『必要な範囲』なのかが国によって解釈が異なっていて、それが自国の行っている武力行使が国際法違反じゃないというロジックに繋がっているのが現状」と越智さんは説明します。
「武力行使の『必要な範囲』を考える際、ここ5年間の自国の安全を考えるのか、それとも100年後の安全を考えるかによって、大きく変わってしまう。その点でロシアやイスラエルは相手国の被害が大きくなっても仕方ないというロジックを持っているのでしょう」
村野さんは戦争を終わらせる要素として、2つを挙げます。
1.戦争相手国に、「これ以上作戦を成功させられない」と思わせる「軍事力=拒否力」
2.多くの国からの支持を得られる「正当性」
戦争は当事者どうしの交渉と合意で終結しますが、「交渉には戦争の軍事的な現実が反映される」と村野さんは指摘します。
「そのため、交渉に至るまでの戦いを有利に進めておかなければいけないが、力がないとそれができない。勝ち筋が見出せない戦争は、同盟国から『この辺にしておいたら』と言われてしまい、国際的な正当性であったり周りからの支持を取り付けることができなくなる場合もある」
私たちの向き合い方—戦後80年の節目に
スマホを開けば毎日、戦争のニュースが目に入ってきます。この時代、戦争というものにどう向き合っていけばいいのでしょうか。
村野さんは「無理のない範囲で、戦争から目を背けずに常に自分のこととして考え続けるのが非常に重要」と指摘します。古代ローマの格言「平和を望むのであれば戦争に備えよ」を引いた上で、村野さんは「戦争について考えずにいれば、戦争が遠ざかってくれるのであればいいが、現実はむしろ逆。戦争について正面から考えることが、逆説的に戦争を遠ざけることになる」と語ります。
越智さんは戦争についての研究書に触れてはどうかと提案します。「戦争について分析するレンズのようなものを手に入れることができます。研究者的な視点で見ることで、心への負担を軽減しつつ、より深く考えられるようになるかもしれません」と助言します。