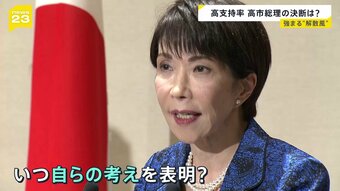絶滅したと思われていた「幻の米」を高校生たちが復活させました。
復活を可能にしたのは、植物の種などを未来に向けて保存する「ジーンバンク」=「遺伝子銀行」とも呼ばれる施設です。その取り組みを取材しました。
■絶滅した“幻の米”「エソジマモチ」 高校生らが復活
9月下旬。宇都宮市内で行われた”幻の米”の稲刈り。

高校生
「そうそうそう!うまくなってきたんじゃない?」
取り組んでいるのは、宇都宮白楊高校の農業経営科の生徒たち。
地元の小学生も一緒に参加しています。
小学生
「すごく珍しいお米だって初めて知りました」
宇都宮白楊高校 農業経営科3年生
「自分たちは貴重な体験ができているなって」
宇都宮白楊高校 農業経営科3年生
「1回なくなった“幻のお米”を収穫できる機会って貴重だと思うので」

子どもたちが収穫しているのは、幻の米「エソジマモチ」。明治時代に、現在の宇都宮市・江曽島地域で生み出されました。
都市開発などもあり、1960年代には生産が途絶え絶滅したと考えられていました。「一度なくなった米」を、どうして復活させることができたのでしょうか?
■“遺伝子の銀行” 17万3000点の“種”保存する「ジーンバンク」
それを可能にしたのが「ジーンバンク」、植物の種や微生物など遺伝子を保存し、未来に残していくために約60年前に作られた施設です。

ーーここはどういう場所になるのでしょうか?
ジーンバンク事業技術室 小柳千栄主査
「こちらは配布用の種子の貯蔵庫になります」
厳重に温度管理され、人が立ち入ることのできない高さ9m・奥行18mの貯蔵庫。
世界中から集められた米や小麦、大豆、野菜の種など毎年およそ1万点もの種が新たに追加され、現在、およそ17万3000点の種が保存されています。

どうしてこれだけの種を保存しているのでしょうか?
ジーンバンク事業技術室 小柳主査
「一度無くなってしまった品種や系統は二度と復活することは出来ないので」
国連食糧農業機関(FAO)の報告によると、この100年の間に地球上の農地から75%以上の品種が姿を消したと言われています。

「ジーンバンク」では温暖化や自然災害に直面した場合に備え、安定した食の供給ができるように種の多様性を守っているのです。
ジーンバンク事業技術室 小柳主査
「病気に強い品種であるとか、我々の健康にとって有益な成分をもっているとか
、そういった可能性を秘めた遺伝資源を保護して守っていかないと」
ジーンバンクの研究員は日本中を周って、保存すべき新たな遺伝子を探しています。他にも農家から譲り受けるなどして、世界中から種を集めています。
ジーンバンク事業技術室 小柳主査
「野菜の種が多いんですけど、ゴボウやニンジン。ウリ科の野菜の種ですとかなり寿命が長いので、今度出てくるのは50年後か100年後かもしれません。私が生きているうちはもう出会えないかもしれない」
「エソジマモチ」も、この施設で保存されていた種の1つです。
ジーンバンク事業技術室 小柳主査
「50粒くらい、グラムにして2~3gほどを配布させていただきました」

たった2gから復活した「エソジマモチ」。2022年には480kgが収穫できるようになりました。