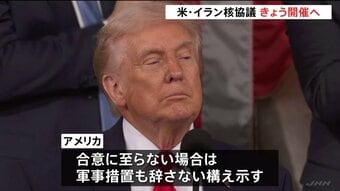予定外に…「お話ししたいのですがよろしいでしょうか」
1日目、七尾市の仮設住宅で愛子さまが住民の集会所の視察を終えた後のことだった。集会所から少し離れたところで、愛子さまを見送るため、そこで暮らす住民60人が集まっていた。予定では、愛子さまは集会所前の車に乗り、次の訪問先へ行くはずだったが、突然、案内役の七尾市職員にこう尋ねられた。
「あちらの方々とお話ししたいのですが、よろしいでしょうか」
そして、50メートルほど離れた住民たちのもとへ歩み寄り、腰をかがめて、笑顔で一人ひとりとじっくり話された。
愛子さま
「旅館の前も通らせていただいたんですが、再開はまだ21館中5館とうかがいました」
「生活が急に変わると大変でしたね」
「(3歳の女の子に対して)何歳ですか。ピンクが好きなの?」
心に刻まれた瞬間だったに違いない。中には涙を流す人もいた。交流した住民らはこう話す。

地元住民
「復興途中のこの町の姿を見てほしいと思っていた。こういう機会があって良かったと思います」
「ただただ嬉しかった。愛子さまから『仮設住宅に入られて、集会所の体操とか行かれていますか』『お体を大切にしてください』とお声がけいただきました。地震から1年半、辛いことや大変なことも多かったけど、生きていく元気をもらいました」

愛子さまに受け継がれるバトン 皇室と被災地
愛子さまには、学生のころから被災地に並々ならぬ思いがあった。2022年、成年会見の際には。

愛子さま(2022年)
「皇室は、国民の幸福を常に願い『国民と苦楽を共にしながら務めを果たす』ということが基本であり、最も大切にすべき精神であると、認識しております。『国民と苦楽を共にする』ということの一つには、皇室の皆様のご活動を拝見しておりますと、『被災地に心を寄せ続ける』ということであるように思われます」

皇室は、これまでも被災地訪問を大切にしてきた。最愛の人を亡くし、住む場所を失った人たちを励まし、支援にあたる人たちを激励する。国民の悲しみと向き合い、「復興に向け勇気づけたい」という思いで寄り添い続ける。こうした考えは、上皇ご夫妻が重視してこられた。
上皇さまは、退位の意向を示したビデオメッセージ(2016年)で次のように述べられている。
上皇さま
「象徴としての役割を果たすためには(中略)、天皇もまた、常に国民と共にある自覚を育てる必要を感じてきました。こうした意味において、人びとの傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えてきました。日本の各地への旅も、私は天皇の象徴的行為として、大切なものと感じてきました」
上皇ご夫妻は災害のたびに各地に足を運び、腰を落として目線を合わせ、地元住民に寄り添われた。『平成流』と呼ばれたそのスタイルは、現在の両陛下の被災地訪問にも踏襲された。


そして今回、愛子さまも集会所で膝をつき、被災者一人ひとりに声をかけられた。上皇ご夫妻の『平成流』所作は、孫である愛子さまにも受け継がれているようだ。公務で初めての被災地訪問、記者はその姿を見て、脈々とバトンが受け継がれているように感じた。