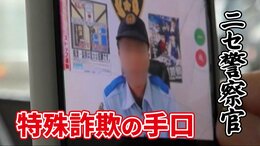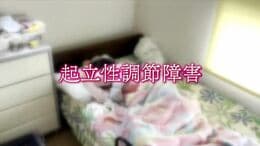里道は区別するため…?右岸から左岸へ移り変わった「白川街道」

地元の方によると、廃道に眠る2つの隧道は明治時代に造られたもので、地区の名前を取って「柿ヶ野第1隧道」「柿ヶ野第2隧道」と呼んでいるそう。
文献に「里道」と書かれていたこの道は、“番所”へ住民が農作物を納めるために利用するなど、地域の暮らしには欠かせない道だったと言います。
また、かつてこの地区に住む人達は、岐阜や名古屋の往来に山越えをして船を利用していました。この不便さを解消するため、明治28年に飛騨川の左岸に「白川街道」を造り、往来しやすくなったと文献には書かれています。
最初に左岸ではなく右岸に道を造ったのは、日当たりが良く、雪が積もっても太陽の光で解けて通行が妨げられないようにするためなのだそう。その後、馬車の普及により道幅が狭くなり、明治28年に白川街道を左岸に新設。その道が開通するまで、右岸の道を白川街道と呼んでいたのだとか。

文献にこの道が“里道”と書かれていたのは、かつて山越えの道を白川街道と呼んでいた時に、別の道であることを区別するため、あえて里道と表記したのではないかと道マニアは考察します。
2025年1月21日(火)午後11時56分放送 CBCテレビ「道との遭遇」より