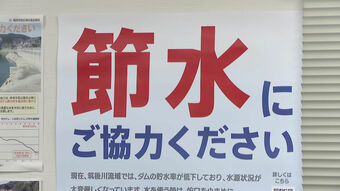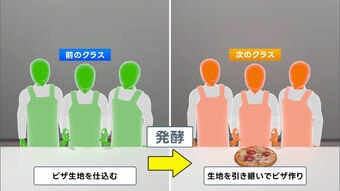3日間限定のパビリオン
このパビリオンは、大手企業でなくとも万博に参加できるように設けられました。
「未来をよくするため」の活動をしていることが条件で、博覧会協会の審査が通れば個人、団体、企業を問わず参加できます。
スペースの使用料は1区画1日22万円から。

他にも、久留米絣を紹介する映像制作や、織機の運送料などおよそ300万円の費用を青年部や組合などで工面しました。

出展はきのうから3日間で、ブースの外では、この日のために作ったステッカーを配り、久留米絣をPRします。
野村織物 野村周太郎さん
「久留米絣が何なのかというものにまず興味を持ってもらって、福岡県の伝統工芸品久留米絣というまず名前から知ってもらうことが一番大切なのかなと」
池田絣工房 池田大悟さん
「将来に残していくとか続けてくために取り組んでいる事業なので、未来につなげていきたいというようなことをずっと続けていかなくてはいけないと思う」
伝統を未来につなげていきたい実は今、久留米絣はある課題を抱えているのです。
課題は生産力の低下

4月23日、福岡県広川町の工房に青年部の姿がありました。
万博に向けての最後の打ち合わせです。
久留米絣協同組合青年部のメンバー
「構想自体は3年くらい前からですね。こうやって価値を広めていこうっていう長期計画の中に万博がある」

国の重要無形文化財に指定されている久留米絣。
今、抱えている課題の一つが生産力の低下です。
最盛期の昭和初期には年間200万反以上を作っていましたが、戦後、洋服が広まり、規模が縮小していきます。
そして近年、追い打ちをかけたのが新型コロナです。
イベントが減り、着物を着る機会も少なくなったため、受注が減少。コロナ禍前、23軒あった製造元が4軒廃業しました。

生産量は新型コロナ流行以前と比べ、3分の1まで減少しました。

160年以上前の江戸時代から続く久留米絣の製造元「丸亀織物」です。現在9人の職人が働いています。
久留米絣は、図案製作、染色、織りなど30の工程があり、分業制で作られていきます。