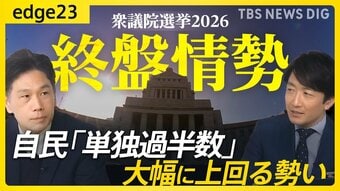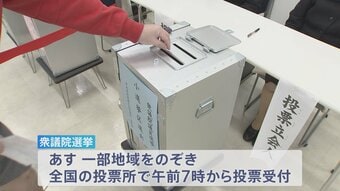多様化する働き方 “静かな退職”のリスクは?
藤森祥平キャスター:
以下が“静かな退職”の例ですが、20代から50代まで多様なきっかけがあります。
▼20代「キャリアアップに興味がない」
▼30代「給料に見合った仕事量はしている」
▼40代「上司と意見が合わない」
▼50代「やりがいがある仕事がない」
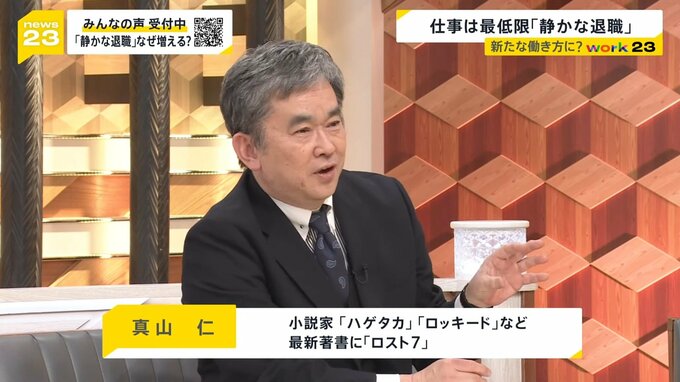
真山仁さん:
私はこの“静かな退職”について、定義をして欲しいと思います。20代と50代では全然パターンが違いますよね。
例えば、自分と同世代の出版社の50代の人たちは、10年ほど前から、「ローンが残っているから業務はするけど、それ以上はやらない」という人がたくさんいます。
20代の、まだ社会人になって間もない人たちが「モチベーションがないからこのままでいい」というのであれば、会社を辞めて、環境を良くして自分の中で楽しいことをするべきだと思ってしまいます。だから、世代で切っていくと定義がしにくいです。
“静かな退職”自体は、その人の人生だから良いと思いますが、問題は、そこに「リスクがある」ということです。例えば、人を減らさなければいけない場合に会社から「やめて」と言われるかもしれませんし、働いている人と働いていない人の給料が同じであることで不満の対象になる可能性もあります。企業は、“静かな退職”を認める代わりに、基本給を減らして頑張ってる人にしっかり払ってあげるべきです。
本来は、全員に同じようにプラスアルファしてあげれば良いのですが、企業はそこまでできませんから、モチベーションがなくなり、だんだん苦痛な環境になるかもしれません。それに耐えられるかは、選択するときに必ず出てくることで、ある意味、(“静かな退職”を選ぶということは)自由を選択したということでしょう。我慢することに対価を払うということが労働の一部ではありますからね。
50代の人は(我慢を)選んでいますが、20代にはこういう選択肢や、「ある上司がいなくなったら楽しくなるかも」と教えてあげたいですね。
小川彩佳キャスター:
若い人にはリスクの感覚はあるのでしょうか?
三宅香帆さん:
リスクの感覚があるからこそ、仕事にフルコミットして上司のもとで働き過ぎても、昇給が認められないから、働かない方が「コスパがいい」と考えてしまうのかなと思います。
藤森キャスター:
深入りする前に判断するということですね。
真山仁さん:
ただ、組織はずっと同じ人間同士で動きません。さまざまな上司がいる中で、どのように楽しいものを見つけるかというのも、社会人の一つの訓練として必要な部分です。
三宅香帆さん:
“静かな退職”モードのときもあれば、上司が変わってやる気が上がるっていうモードのときもあるという気がします。
真山仁さん:
“静かな退職”は本人の自由なので構わないんですが、同世代で「自分はこんなに働いているのになんで同じ給料なんだ」となれば、働いている人たちが辞めてしまいます。