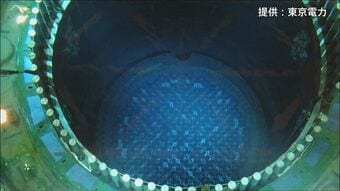日本と中国の関係がいま、大きく変わりつつあります。最大の要因はトランプ政権の誕生です。貿易摩擦などで厳しくなるアメリカとの関係を見据え、中国は今、日本だけでなくこれまで対立していたインド、オーストラリアなどとの間でも懸案を解決し、関係を安定化させようとしています。
高まる友好ムードの先に何があるのか。残された課題にどう向き合うのか。金杉憲治駐中国大使に日中外交の舞台裏から米中関係、中国の魅力まで縦横無尽に語り尽くしてもらいました。
後編は中国経済の課題、習近平国家主席の素顔についてです。
(前・後編のうち後編。毎週水曜日に配信:JNN北京支局のポッドキャスト「北京発!中国取材の現場から」より抜粋・再構成)
(3月18日に北京の日本大使公邸で収録)
経済成長率「5%」の旗が下せないわけ 中国経済の実態と今年の課題

Q3月上旬に開かれた全人代=全国人民代表大会。どこに注目しましたか?
金杉大使
結果的には人事も含めてあまりサプライズがない全人代だったなというのが私個人もそうですし、多くの外交団の人がそう思っていると思います。
Q中国政府の掲げた経済成長率目標「5%前後」はどう思われましたか?
金杉大使
今の中国の目標が2035年までに「中程度の先進国」になるということで、それを達成するためには毎年5%弱の経済成長が必要だというのが目標なので、中国としてはどうしても5%成長という旗は下ろせないですし、実際、昨年後半にかけて相当経済刺激策をとって5%を達成していますので5%という数字はだいたい予想されていたんだろうなと思います。
Q「内需の拡大」「消費の押し上げ」が重点になっていましたがこの点はどう思われますか?
金杉大使
中国は今、内需不足、消費者が買い控えに走っているということで、内需を他の国と同じぐらい大きなものにするというのは国として大事な役割だと思うんですけれども、他方難しいのは去年中国がやった家電製品の買い替え促進や設備投資の更新というのは、補助金が切れてしまうと需要を先食いしている形なので一挙に需要が悪くなるというのは日本でもそうでしたから、どういった形で内需を刺激していくのか、消費マインドを高めていくのかというのはどこの国にとっても難しいと思います。
一番難しいのは不動産の調子が悪いので「負の資産効果」と言いますけれど、不動産が盛んな時は不動産から生まれる資産を消費に回すことができましたが、今は不動産価格がどちらかというと下がっていく方向なので、どうしても人々が資産を守る、貯蓄の方に回してしまう。不動産問題が解決していくかどうかというのは我々としても見ていかなければいけない部分かなと思います。
Qもう一つの懸念材料はアメリカですよね。李強首相も「一国主義」「保護主義」という言葉を使ったり、「国際経済の循環を阻害している」と、これは暗に関税のことを言っているのだと思いますが、中国経済にとって不安定要因になりますか?
金杉大使
ただ中国は前回のトランプ政権の時、関税の応酬がありましたけれども、それが中国経済にそれほど否定的な影響は及ぼさなかったので、関税の打ち合いのようなことであれば、自分たちとしても当然準備をして備えているというのはよく見て取れると思います。

Q中国経済へのダメージは小さくて済むのでしょうか?
金杉大使
今は多分そうだと思います。中国製品は価格競争力がありますから少しの関税がかかったとしても影響は大きくないというのが多分今の判断ではないでしょうか。あとは他のマーケットの開拓ですね。アフリカ、中東、東南アジア。そのあたりのマーケットの開拓はこの数年大変活発にやってきていると思います。アメリカのマーケットで多少失うものがあるとしても、それは他の市場で十分補えるということではないかと思います。