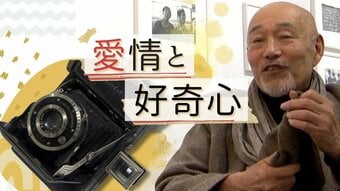緊張は、生物の自己防衛反応
誰しも経験したことがあるであろう「緊張」。そもそも緊張とは、どういう状態のことをいうのか。

アイさくらクリニック 木村昌幹 院長
「恐怖や強いストレスなどを感じると、交感神経の機能が高まってノルアドレナリンやアドレナリンが放出され、瞳孔が開いたり、筋肉内の血管が拡大したりします。緊張は、生物が自己防衛反応として生じる反応で、悪いものではない。むしろ、集中力を高めるための仕組みともいえます」
集中力を高めるための仕組み、ともいえる「緊張」だが、その緊張や不安が非常に強く、耐え難いと感じている場合は「社交不安障害」と診断されることもある。
感じるストレスには個人差があるため、緊張する人のすべてが、社交不安障害と診断されるというわけではない。
アイさくらクリニック 木村昌幹 院長
「社交不安障害の人は、様々な場面で通常よりも強い緊張や不安を感じます。人前でスピーチをしたり、目上の人と話をしたりする時だけでなく、電話や会食、お腹が鳴ることにも恐怖を感じる人もいます」
院長の木村医師は、子どもの頃の記憶が引き金になっているケースもあると話した。
アイさくらクリニック 木村昌幹 院長
「社会人になっても緊張を苦痛に感じる人の中には、子どもの頃の記憶が原因になっているケースもあります。例えば、『発表がうまくできなかった』『顔が赤くなるのをからかわれた』など恥ずかしい思いをした人は、大人になってもその記憶がよみがえり、過度な緊張を感じることも少なくありません」
「ママ友トラブル」や「PTAトラブル」も引き金に?
また、「ママ友からの誘いを断れない」、「PTAの会合で発言するのが苦痛」といって心身の不調を訴え受診し、「社交不安障害」と診断される人も増えていると話す。
自分のことであれば回避できるが、子どもの習い事や学校行事、PTAなどは「子どものことだから、避けられない」。そう感じてそのプレッシャーが苦しさにつながってしまうという。
ではどうすればいいのか。