文部科学省によると、昨年度県内の小中学校の不登校の児童・生徒の数は、前の年度から1251人増え7013人で過去最多を更新しました。
学校に行くことが難しい子どもが年々増加する中、当事者と保護者を社会から孤立させないための”居場所”の重要性が高まっています。

▼長嶺さんと保護者
「来週は学校行ける?卒業式のリハーサル」
「今日もリハーサルと言っていました」
「どこかでいけたらいいね」
小学6年生の子どもが「あいのいえ」に通う山内恵利さん。
子どもから「学校にいきたくない」と伝えられた時、親としてどう接するべきか悩んだといいます。
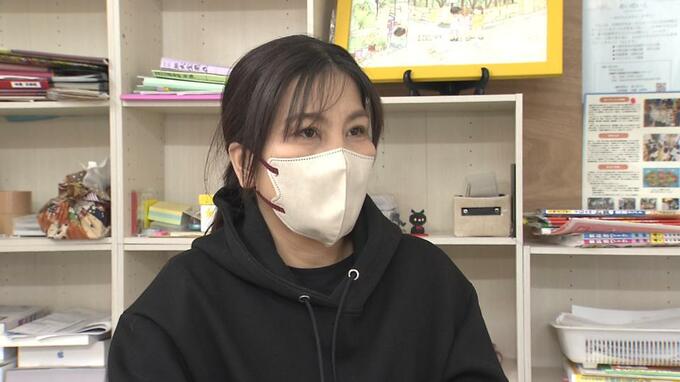
▼山内恵利さん
「子どもが自分の気持ちを私に伝えたのは『箱の中にいるみたい。窮屈すぎる息ができない』それくらいだった。学校を地獄に捉えた。子どもは。そこまで学校がこの子にとって遠ざかってしまっているのかなって。私も葛藤する時期でした」
通い始めてから前向きな言葉も増えたといい、山内さん親子にとって「あいのいえ」は大きな支えとなっています。
▼山内恵利さん
「(不登校の子は)自分に価値がない、私は社会に認められていないと思ってしまう。その喪失感や不安が少しずつ溶けていっているような感じがします」
▼あいのいえ長嶺加恵美代表
「寄り添うという言葉がよく知られているが、その寄り添い方というのも千差万別で子どもたちのニーズや状況が違うのでそこに目線をあてて子ども目線で接していくというのが大切」
家庭や学校に代わる「第3の居場所」として子どもたちが安心して学べる環境を提供する。この取り組みはSDGsの目標につながっています。

▼「あいのいえ」に通う子
「いっぱいここにゲームがあって、カードゲームとか遊んだりみんなで楽しんだりしている」
「みんなで遊んだりするのが一番楽しい」
▼あいのいえ長嶺加恵美代表
「私たち1人ひとりがそれぞれの立ち位置で何ができるか。私はよく『寝かさない』という言葉を使うが、つまり孤立させないということ。そこは大事にしていきたい。子どもたちは地域の宝という感覚をもっていけたら」
子どもたちを社会から孤立させないために、多様な学びの形が必要とされています。
▽取材メモ
「あいのいえ」では学習に困難を抱える子どもたちをサポートする教材を開発しオンラインで無料公開していて、4月以降、あいのいえのHPから利用登録が可能だということです。
代表の長嶺さんは、子どもたちが自立への一歩を踏み出す足がかりになればと教材の活用を呼びかけています。
(取材:仲田紀久子キャスター)














