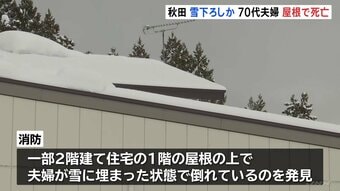初マラソンの近藤亮太(25、三菱重工)が日本人トップの2位と健闘し、9月開催の東京2025世界陸上代表候補に躍り出た。大阪マラソン2025は2月24日、大阪府庁前をスタートし大阪城公園内にフィニッシュする42.195kmのコースで、東京2025世界陸上選考会を兼ねて行われた。優勝はイフニリング・アダン(28、エチオピア)で、近藤とのデッドヒートを2秒差の2時間05分37秒で制した。近藤は2時間05分39秒の日本歴代5位、初マラソン日本最高記録の快走だった。
細谷恭平(29、黒崎播磨)も2時間05分58秒と日本歴代7位の好記録。日本人3位、全体6位の黒田朝日(20、青学大)も2時間06分05秒の学生新。菊地駿弥(26、中国電力)、鈴木健吾(29、富士通)、柏優吾(24、コニカミノルタ)も含めた日本人6選手が東京2025世界陸上参加標準記録(2時間06分30秒)を突破した。
全日本実業団ハーフマラソン日本人トップなど年に一度の快走
最終的には3月2日の東京マラソンの結果によって変わってくるが、近藤は大阪マラソン終了時点で世界陸上代表3枠の圏内にいる。だが近藤は世界陸上代表まで意識してレースに臨んではいなかった。「タイムは2時間08分00秒が目標でした。テーマとしては30kmまで余裕を持ち、最後まで体の軸をぶらさずに走ることを考えていました。30kmまで先頭集団に付くことができれば、そこから足が止まっても2時間8分は出せる」そう考えて走った結果が2時間05分39秒である。
近藤は入社3年目だがニューイヤー駅伝には一度も出場していない。同駅伝の経験がない実業団選手が、マラソンで2時間7分未満の記録を出したのは史上初めてだ。それができたのは、三菱重工だからだろう。三菱重工はこの10年で、ニューイヤー駅伝入賞常連チームに成長した。主要区間の選手は日本トップレベルだが、近藤は1年目の終わりの全日本実業団ハーフマラソンでチーム最高記録(1時間00分32秒)で日本人トップの3位となった。メンバー入りする力はあった。
3年目は足底の痛みの対策として10月の約3週間を休養に充てたことが理由だが1、2年目のメンバー漏れは「戦うぞ、という気持ちを出せていなかった」と近藤は自己分析している。最終的にはメンタルということになるのかもしれないが「練習でも力みが出ることがありましたし、特に試合では“やるぞ”という気持ちが強く、上半身に力が入ってしまう」ことも要因だった。力を入れようとすると走りが崩れ、メンバーを決める重要な練習でスタッフの信頼を勝ち取ることができなかった。
順天堂大学時代も「練習では強い」と言われながら、箱根駅伝出場は4年時だけ。アンカーの10区で2位のフィニッシュテープを切ったが、近藤の区間順位は14位と振るわなかった。それでも「入社後は年に1回良い走りができていた」という。1年目は前述の全日本実業団ハーフマラソン、2年目は10000mで自己記録を35秒更新した佐賀県長距離記録会(28分16秒14)、そして3年目が今回の大阪マラソンである。「1年に一度、自分でもビックリします」しかし今回は、快走する手応えも感じて臨んでいた点が、過去2回のビックリとは大きく違っていた。
ニュージーランド合宿で得られた手応え
その手応えを得たのは、ニュージーランド合宿中の1月22日だった。大阪マラソンに一緒に出場した定方俊樹(32、三菱重工)と「6回の40km走の最後の1本」を行っていた。定方は12回のマラソン歴があり、2時間7分台で2回、8分台も2回走った選手である。「定方さんに全部引っ張ってもらって、後ろで走らせていただきましたが、その中で余裕を持つマラソンの走り方を、いかに楽に走るかをつかむきっかけがあったんです」
それまでは前を走る選手の首や背中の上部、さらにはコースの前方を見ていた。それを定方の「お尻を見ること」に変更した。力を使わない走り方をしようと集中した結果、視線が自然と先輩のお尻に行った。「お尻を見ることで上半身が前傾できて、軸がぶれなくなり楽に走ることができました」
中学時代から長い距離の方が強かった。「800 m、1500mでは勝てない相手に、3000mでは勝つことができました。距離が延びれば勝てるから、一番長い距離のマラソンをいつかやろうと、安直に考えていました」本人は「謎の自信がありました」と笑うが、おそらく当時から、速く走ろうと考えると上半身が起きたフォームになり、力みが出やすかったのだろう。それは実業団入り後も同じだった。「長い距離で遅めのペースなら、楽に走ることができていました。しかし1km3分ちょっと、3分を切るようなペースになるとその走り方ができませんでした」過去2回の快走では、“楽な走り方”が無意識にできていた。
入社1年目の全日本実業団ハーフマラソンは「初めて時計を付けずに走ったレース」だった。「自分の走りとリズムに集中」ができた。入社2年目の10000mの大幅自己新は今思えば「たぶん何も考えずに、ペースメーカーのお尻を見ていた」のだと推測している。3回目の今回は、その走りを意識的にできた。「どう力を使うかを考えてばかりいましたが、力を抜いたらいいのだとニュージーランドの40km走で気づきました。その後はスピードの速いメニューでも、その走りができるようになった」
大阪マラソンでも時計は付けず、集団のリズムに合わせることで楽に走ることに集中した。定方をはじめ、細谷や小山のお尻を見て「ペースメーカーの細かい上げ下げに左右されずに走れた」という。30km過ぎの折り返しの誘導ミスも、「まったく気づかないくらいに集中」していた。