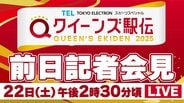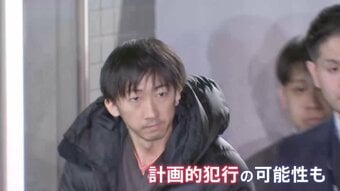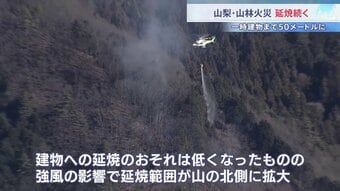厚底シューズへ対応する動きとトレーニング
昨年の今大会で、山西は競技人生初の失格を経験し、パリ五輪代表も逃した。19年ドーハ、22年オレゴンと世界陸上を連覇、21年の東京五輪も銅メダルを獲得し、歩型が崩れないことが武器だった山西にとって、大きなショックを受ける出来事だった。
競歩界でも22~23年頃から、厚底シューズ着用選手が活躍し始めた。従来の薄底シューズでも日本選手は記録を出していたこともあり、新シューズへの移行を躊躇っていたところもあった。山西も23年のブダペスト世界陸上(24位)の後に一度、厚底シューズを試したが、昨年の今大会に間に合わないと判断して薄底シューズに戻して出場した。しかし厚底シューズを試す過程で歩型が崩れてしまい、戻すことができずに失格してしまった。
陸上競技で給料をもらう選手として、代表を逃したら競技をやめる覚悟で競技を続けてきた。しかし「一度の失格で心が折れるのはダサい」と競技継続を決意。夏の代表試合出場がなくなったことで、腰を落ち着けて厚底シューズ対策に取り組んだ。
走る動作では接地の際に重心に乗り込んで、その反発で前方に弾んでいく。しかし競歩では両脚が地面から離れたら歩型違反になる。弾むのでなく、後方に足を擦るように動かすために、山西は「意識的に踏んでいく」という接地の仕方を行う。
「(具体的な動きとしては)つま先の方に押すというより、自然とその位置に体重が乗る姿勢を作り、加重のタイミングを探っていきます」
5月のスペイン・ラコルーニャの20km(1時間17分47秒でパリ五輪メダリスト3人に勝利)でその歩き方を試し、9月の全日本実業団陸上10000m、10月の全日本競歩高畠20kmの優勝でも、その精度を高めようと歩いた。
「ラコルーニャではまだ(完成度は)3割くらいでした。練習で良いときもあれば、今日は良くなかったというときもあって、バラつきが大きかった。高畠を経て冬期練習の中で、そのバラつきが小さくなりました」
ラコルーニャの前にもポーランド・ワルシャワの試合にも出場したが、イタリアを拠点にトレーニングを行いながら試合に遠征した。東京五輪金メダリストのマッシモ・スタノ(32、イタリア)と一緒にトレーニングを行い、「ヨーロッパ選手との身体的な違いや自分の武器、日本人のやるべきトレーニングの方向の違い」も再確認しながら、厚底シューズ用のトレーニングも学んだ。
「(接地で)踏み潰さないといけないので、パワーも必要になります。重りを持つトレーニングを定期的に入れたりして、姿勢や踏み方を変えてきました」
世界記録を出したから世界陸上でも勝てるわけではない。オリンピックや世界陸上では前半がスローになり、後半でペースアップする展開が、国内レースと大きく異なる。その中でもペース変化が激しい。
しかしオレゴン世界陸上では、山西もその展開に対応して1時間19分07秒で勝ちきった。そのときのラスト1kmは3分41秒で、今回は世界記録ペースの中で3分43秒だった。これまでは世界大会に対して「逆算して」ピークを合わせてきた。今回ももちろん同じやり方になるが、目の前の大会を1つ1つ楽しむ気持ちも強くなっている。
「またチャンスをいただけたので、新しいトライとして(東京2025世界陸上も)優勝を狙いたいな、と思います」
世界陸上で過去、2回優勝した日本選手は山西1人しかいない。さらに新たな歴史の1ページを記す準備が進んでいる。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)