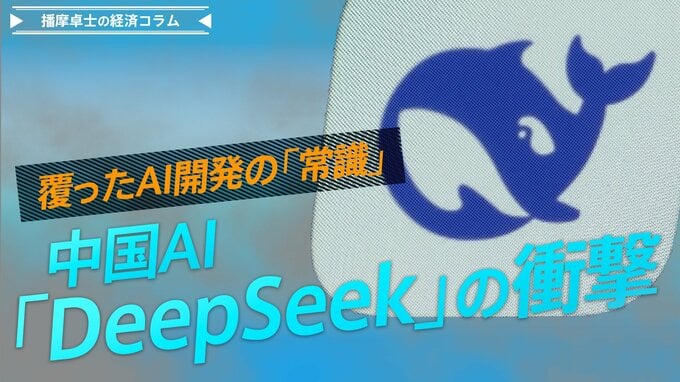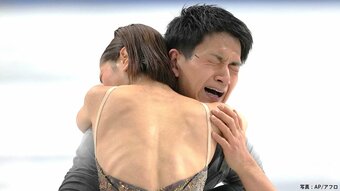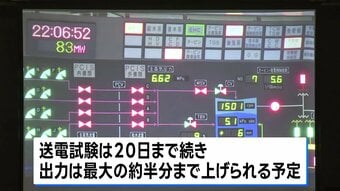「AI競争におけるスプートニク・ショックだ」という文字が米メディアに踊りました。スプートニク・ショックとは、米ソ冷戦期の1957年に、旧ソ連が人工衛星スプートニクの打ち上げに世界で初めて成功し、自らの技術優位を信じ切っていたアメリカ国民に大きな衝撃を与えた出来事のことです。
中国のスタートアップが開発した「DeepSeek(ディープシーク)」が、、アメリカのオープンAI社の「Chat(チャット)GPT」を超えるとも言われる性能のAIを、しかも10分の1以下のコストで開発したというニュースは、AI開発のルールを変えたとして、ワシントン、ウオール街、そしてシリコンバレーに大きな衝撃を与えました。
ChatGPTに匹敵、コストは10分の1以下
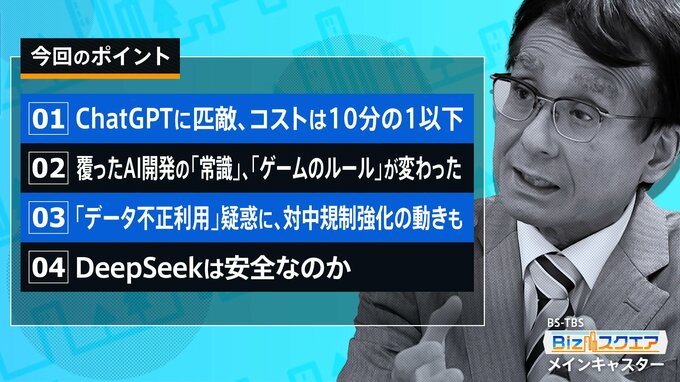
中国のディープシークは、1985年生まれの梁文鋒氏が、2023年に浙江省杭州市で創業した新興企業です。このスタートアップが開発した「ディープシークR1」というモデルが、アメリカでトランプ大統領の就任式が行われた1月20日に発表されました。
同社によれば、R1は主な性能で米オープンAI社のチャットGPTに並ぶか、それを凌ぐ一方、その開発費は560万ドル、8億6000万円だったとしています。この額は、オープンAI社が「GPT4」にかけた開発費7800万ドルの14分の1、グーグル社の「Geminiウルトラ」の開発費1億9100万ドルの、なんと35分の1に過ぎません。
これが本当なら、「AI開発にはカネがかかる。従って、世界から資金が集まるアメリカの優位性は揺るがない」という、いわば「神話」が崩壊することになります。
覆ったAI開発の「常識」、「ゲームのルール」が変わった
こうした事実が明らかになった27日、アップ・ストアの無料ダウンロード回数で、「ディープシーク」が、「チャットGPT」を抜いてトップに立ちました。
翌28日には株式市場にはショックが走りました。アメリカのAI関連株が軒並み売られ、中でもAI用半導体を一手に引き受けるエヌビディア株は1日で17%も下落、エヌビディアの時価総額は1日だけで、90兆円以上も失われたのです。
それはそうでしょう。これまでの「常識」が覆されたからです。その常識とは、「AIの開発には、多くのことを学習させなければない、そのためには大量のデータセンターが必要で、金と時間がかかる。そして、効率よく学習させるためには、同時並行的に処理ができるエヌビディア製のGPUという半導体が欠かせない」というものです。
つまり、エヌビディアの高性能の半導体が手に入らない中国企業には開発できないはずでした。本当なら、いわば「ゲームのルール」が根本から変わったことになります。