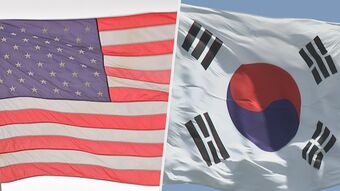厚生労働省などによりますと、去年1年間に自殺した人は、暫定値で前の年から1569人減って2万268人となり、統計を開始して以降2番目に少なくなりました。
一方、小中高生の自殺者数は527人で、統計のある1980年以降で最も多くなっています。男子は前の年に比べて20人減っているのに対し、女子は34人増加しています。
精神保健福祉士で、悩み相談を受ける側のサポートなども含め「若者の自殺対策」に取り組むNPO法人「Light Ring.」の代表理事・石井綾華さんは、小中高生の自殺者数が増加傾向にある要因のひとつとして、子どもたちの「人間関係の複雑化」を指摘しています。

デジタル時代を生きる子どもたちの生きづらさ
ーー小中高生の自殺者数が過去最多となりました。背景にはどのようなことがあると考えられますか?
「自分たちが活動する中で、成績や進路の悩みに加えて、人間関係で悩む人の数が増えたというふうに実感しています。
学校は子どもたちにとって非常に生活時間が長く、トラブルが起きやすい環境でもあります。学校といっても実際に対面で接する時間と、それ以外にオンラインでクラスメイトと繋がる時間など、様々な場面で人間関係のトラブルが起きやすい環境であるというところにも目を向ける必要があると思います。SNSによるトラブルは大人の目が届きづらいというところも問題の一つです」
ーー今や自分のスマホを持っている子どもも少なくないですが、インターネットの利用による影響は他にもあるのでしょうか?
「SNSの発展に伴って、他人と自分を比較してしまう子も増えていると思います。他人と自分を比べて、体重や容姿などに劣等感を抱きやすくなったり、フォロワー数やいいねの数など、そういった面からも比較しやすくなっていて、『自分は必要とされていない』『自分は駄目な人間だ』ということを思いやすい傾向があるのではないかと思います」