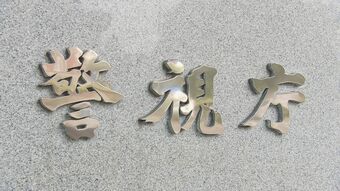“桁違い”な制作費が及ぼす影響とは
野村:Netflixによるコンテンツ投資はどんどん盛んになるのでしょうか。
中山:僕もNetflixに2回3回ぐらい執拗に聞きました。日本でいくら使っていますかって。でも、教えてくれないですね。一方、日本のテレビキー局のドラマ制作費はNHKも含めて全部足したら300億ぐらいあったはずです。
野村:6局足した1年間の制作費ですか。
中山:Netflixの1年間の韓国でドラマを作っている制作費(1兆~1.5兆円)に負けていますよね。1作の単価がだいぶ違いますが、日本って300本とか作っているので。1本当たり1億円ぐらいでしょうか。逆にNetflixは1時間あたり2~3億円ぐらい。1作品で15億とかだから、すごいお金のかけ方ですよね。
野村:一点豪華主義じゃないですけど、お金かかっているなって作品を作った方がヒットするということですかね。
中山:初期の「いろいろやろうぜ」から進化して「ガンガンいこうぜ」になってきているかなと思います。ただ、近年は「守りを大事に」という流れにもなってきていますね。
野村:Netflixが日本の中で頭ひとつ抜けましたが、日本のクリエイターにはどんな影響がありますか?
中山:僕はテレビ社会の競争の中で吊り上げられたことによる「ちゃんとお金かけようね」という意識があると思います。TBSを代表に『VIVANT』から本当に予算をかけていますよね。勝負しようという中で競争が生まれています。
Netflixの台頭によって見えてきたのが、日本のなかで「テレビ局横並び」という環境がよくなかったんだと思うんですよ。クリエイターにとって、チャンスが増える、日本以外でヒットするかどうかというのが未来を開かせると感じます。
一方で『ゴジラ-1.0』のようなお金をかけないヒット作も生まれています。ワーナー映画は150億円ぐらいかけている一方で、『ゴジラ-1.0』の予算は15億円ほど。10分の1の制作費なのに、売り上げ的には3分の1ぐらいまで達しています。掛けた金額が全てではないですが、その工夫の確立によってバラエティーができること自体はプラスしかないと僕は思っています。