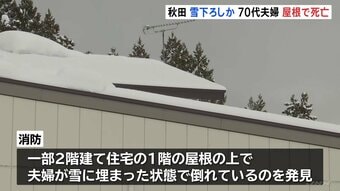今やすっかり“メジャーリーグの顔”へと飛躍を遂げた大谷翔平。メジャー挑戦当初からこれまで、日々の取材現場でも様々な変化があった。球団の取材対応、日米メディアの大谷への接し方、そして大谷自身も。それらを長年最前線で目撃してきたスポーツニッポン新聞社のMLB担当で大谷番の柳原直之記者が変化の軌跡を振り返る。
日米の取材ルールの違いとエンゼルス球団の特例
スポーツニッポン新聞社(以下、スポニチ)の野球担当の記者として、2014年に日本ハム担当となってから、メジャー移籍後の今も大谷翔平を追い続けて2024年で11年目を終えた。
投打二刀流で2021年、2023年にMVPに輝き、2024年は史上最速で「40―40(40本塁打、40盗塁)」に到達したどころか、前人未到の「50―50」を達成。最終的には最大の目標に掲げていたワールドシリーズを制覇、そして3度目の満票MVPを受賞した。
一生に一度どころか、もう今後二度と出てこないかもしれないような偉大な選手と相対し、直接、質問を投げかけて思いを聞くことできる毎回の機会に、感謝の念は尽きない。
本稿では大谷を支える球団、毎日のように大きく報じるメディアの取材現場などの変化の軌跡を振り返っていきたい。
筆者が大谷を初めて取材したのは遊軍記者時代の2013年。当時日本ハムのルーキーだった大谷は既に二刀流で多忙を極め、球団の方針で取材は1日1回に限定されていた。雑談を含めた日々のマンツーマン取材も禁止されていた。
一方で、活躍した日はもちろん、4打数無安打の日も、代打で凡退した日も、基本的には、帰りの札幌ドームの選手駐車場などで大谷は立ち止まり、報道陣の質問に答えていた。
メジャーリーグに舞台を移した2018年以降、新たな所属先となったエンゼルスは日本ハムのこのルールを参考にした。
メジャーリーグでは、選手がグラウンド内で取材を受けることは日本に比べて極端に少ない。日本とは違い、基本的には試合前後、キャンプ中であれば練習前後のクラブハウスで取材を受けることになっている。それがメジャーリーグのしきたりでありルールであり、どんなスター選手でも、タイミングさえ合えばマンツーマン取材が可能だが、エンゼルスはこれを禁止するという大きな決断を下した。
ルーキーイヤーは球団広報、日米メディアはともに手探り状態だった。日本メディアはテレビ、新聞、通信社を含めると最低でも常に20人以上いて、エンゼルス担当の米記者は大リーグ公式サイト、オレンジカウンティ・レジスター紙、ロサンゼルス・タイムズ紙、スポーツサイト「ジ・アスレチック」の4人が“常駐”。その他にもコラムニストやナショナルライターと呼ばれる著名な米記者も多数訪れていた。
大谷の入団後、ドジャース時代に野茂英雄の担当広報で、日本人の両親を持つグレース・マクナミーさんが新たにエンゼルスの広報として着任した。英語と日本語が話せる広報として大谷、球団、日米メディアの「橋渡し役」として尽力。しかし、各メディアから多種多様な要望に全て応えるのは、端から見ていても無理難題だった。
この年はメイン球場「ディアブロ・スタジアム」の右翼後方に大谷の会見や日本メディア向けの仮設テントが設置された。当時のティム・ミード広報部長が「ここで大谷選手が毎日、話す」と話していたが、それが簡単なことでないことは多くのメディアが感じ取っていた。
マクナミー広報は1年目こそ、監督会見を全て日本語に訳そうとしていたが、会見のテンポが悪くなることから途中から必要時だけ介入するようになった。その他に、2年目から仮設テントそのものが廃止になった。
大谷はシーズンが始まると、毎日ではないにしろ、積極的にメディアの前で話した。1年目は球場内の会見場だったが、2年目以降は会見場所までの移動時間を省くことを目的にクラブハウス前の球場通路に変更。原則、雑談すら出来ない状況であったため、大谷の本心を聞くことはできなかったが、慣れないメジャーの環境に加え二刀流で多忙を極める中、可能な範囲で対応してくれている印象だった。